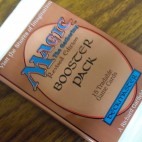ご無沙汰しています。よしおです。
SNSでDNのサービスが3/31をもって停止するというお話を耳にしました。
最近はこういった日記ブログサイトは、MTGの攻略記事も含め文章に金銭的価値を見出している人が増えているようで、有料記事にできるサイトに移行していったのだと推測されます。
ニコニコ動画から収益化できるYouTubeに流れたり個人でできる有料ファンサイトが増えてきたりしているのと似た流れですね。
数年利用していたので愛着はありますがこれも時代の流れだと割り切り、最後に自分もこちらで挨拶をもって締めくくろうと思います。
ここで自分が日記を書き始めたキッカケは、ネットでMTGのレガシーについての攻略を調べている時にDNが出てきて参考にしていたのと、以前からのレガシー仲間がこちらで考察や戦績を書いているのを見て触発された、というものでした。
MTGに関しては当時から元々自分なりの考えや想いや拘りがあったので、自分も考察した内容を発信したり戦績を残す目的で始め、熱心だったときは新セット毎に個人的な注目カードや新デッキの構築、月に1回以上は大会に参加して戦績と感想を書き残していました。
考察に関しては当たり外れもあり考え方の違いもあったりするのでここでは割愛しまが、では戦績はというと、小規模の大会では細かく結果を残せたものの大きい大会でそれなりの実績と言えるものは、
2015年GP神戸のレガシー選手権でスイスラウンド2位の1没(BUG続唱)
2016年KMCで8位になりデッキ掲載(グリクシスパイロマンサー)
2017年エターナルパーティで9位(グリクシスパイロマンサー)
と、現時点ではこの程度に留っています。
2013年ごろからレガシーを始めた自分にとってグリクシスというカラーが最も思い入れがあり、デルバーを用いたテンポ型であったり中速ヤンパイ型であったりを試行錯誤して結果を残せていた時期が自分にとって一番楽しかったと言えます。
大会に向けて切磋琢磨したり一緒に調整をしてもらえるメンバーにも恵まれ、とても充実したMTGレガシーライフを送ることができていました。
さてここからが本題ですが、レガシーの未来についてと自分自身のレガシーに対する今後の向き合い方について少しお話ししようと思います。
2019年以降は特殊セットであるモダホラを皮切りに意図的なインフレによって本来自分が好きだった元々のレガシーの形とは徐々に変化していき、モチベーションも当時より落ち着き始めDNの更新も徐々に減っていた中で、追い打ちをかけるかのように訪れたコロナ禍。とうとうテーブルトップの大会にほとんど参加することがなくなってしまいました。
それでも新セットは必ず追いかけ、コツコツ買っては一人回しや兄と調整は密かに続けていました。
去年に自分の実生活の環境にも大きな変化があり、今までのように注目したカードを闇雲に買い漁るという事をしなくなり、それに加えてモダホラ2のインフレの加速による環境の変化に追いつけなくなっていく自分がいました。
例えばラガバンはスポイラー時点から明らかに目に見えたオーバーパワーカードで、価格も初動から高額。レン6のようにモダンで禁止にならなければ価格は維持できるでしょうが、レガシーで1年以内に禁止になるであろうカードを気軽に買うことに引け目を感じ、禁止になるまでは環境に取り残されて土俵に立つのが難しいという状況に陥ってしまいました。
このような背景があり以前より積極的に新カードや新デッキを試す機会というのが確実に減り、同時にレガシーに向き合う時間も減っていきました。
そんな意図的な特殊セットによるインフレは、残念ながら自分にとってレガシーには望んでいない方向に進んでいます。これが原因でMTGから離れてしまった仲間やプレイヤーも見ました。
自分もそれならばと一瞬よぎりましたが、MTGが趣味として好きな気持ちはどうしても変わらなかったので、やはり無理に追うことはせずに禁止改定によってしっかりと調整が行われた環境に戻った時にまったり楽しんだりたまに大会に出るというスタンスに切り替え、最悪このままインフレの加速状態が変わることがなければ、引退までとはいかずとも大会に出ることはせずこのまま身内だけで楽しむ程度に留めるか、カードを寝かせ休止してしまう事を視野に入れてもいいかなと思っています。
レガシーを通じて気の許せる仲間ができたのも事実です。この仲間がいなければカードやデッキに対する評価や考え方、プレイングは絶対に磨かれることはなかったでしょう。レガシーを楽しむことにおいてこうした仲間の存在が一番のモチベーションになっていたのは間違いありません。
仮にレガシーを休止したとしても仲間との関係は休止するつもりは全くないので、人との繋がりは今までと変わらず大事にしていきたいなと思います。
最後になりますが、今まで自分の日記を見てくださったりコメントしてくださった方々、本当にありがとうございました。
現在レガシーに関する考察等は、変わらずツイッター(@screamo0116)で細々と続けていますので、コメントも大歓迎ですし今後も暖かく見守っていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
では。
SNSでDNのサービスが3/31をもって停止するというお話を耳にしました。
最近はこういった日記ブログサイトは、MTGの攻略記事も含め文章に金銭的価値を見出している人が増えているようで、有料記事にできるサイトに移行していったのだと推測されます。
ニコニコ動画から収益化できるYouTubeに流れたり個人でできる有料ファンサイトが増えてきたりしているのと似た流れですね。
数年利用していたので愛着はありますがこれも時代の流れだと割り切り、最後に自分もこちらで挨拶をもって締めくくろうと思います。
ここで自分が日記を書き始めたキッカケは、ネットでMTGのレガシーについての攻略を調べている時にDNが出てきて参考にしていたのと、以前からのレガシー仲間がこちらで考察や戦績を書いているのを見て触発された、というものでした。
MTGに関しては当時から元々自分なりの考えや想いや拘りがあったので、自分も考察した内容を発信したり戦績を残す目的で始め、熱心だったときは新セット毎に個人的な注目カードや新デッキの構築、月に1回以上は大会に参加して戦績と感想を書き残していました。
考察に関しては当たり外れもあり考え方の違いもあったりするのでここでは割愛しまが、では戦績はというと、小規模の大会では細かく結果を残せたものの大きい大会でそれなりの実績と言えるものは、
2015年GP神戸のレガシー選手権でスイスラウンド2位の1没(BUG続唱)
2016年KMCで8位になりデッキ掲載(グリクシスパイロマンサー)
2017年エターナルパーティで9位(グリクシスパイロマンサー)
と、現時点ではこの程度に留っています。
2013年ごろからレガシーを始めた自分にとってグリクシスというカラーが最も思い入れがあり、デルバーを用いたテンポ型であったり中速ヤンパイ型であったりを試行錯誤して結果を残せていた時期が自分にとって一番楽しかったと言えます。
大会に向けて切磋琢磨したり一緒に調整をしてもらえるメンバーにも恵まれ、とても充実したMTGレガシーライフを送ることができていました。
さてここからが本題ですが、レガシーの未来についてと自分自身のレガシーに対する今後の向き合い方について少しお話ししようと思います。
2019年以降は特殊セットであるモダホラを皮切りに意図的なインフレによって本来自分が好きだった元々のレガシーの形とは徐々に変化していき、モチベーションも当時より落ち着き始めDNの更新も徐々に減っていた中で、追い打ちをかけるかのように訪れたコロナ禍。とうとうテーブルトップの大会にほとんど参加することがなくなってしまいました。
それでも新セットは必ず追いかけ、コツコツ買っては一人回しや兄と調整は密かに続けていました。
去年に自分の実生活の環境にも大きな変化があり、今までのように注目したカードを闇雲に買い漁るという事をしなくなり、それに加えてモダホラ2のインフレの加速による環境の変化に追いつけなくなっていく自分がいました。
例えばラガバンはスポイラー時点から明らかに目に見えたオーバーパワーカードで、価格も初動から高額。レン6のようにモダンで禁止にならなければ価格は維持できるでしょうが、レガシーで1年以内に禁止になるであろうカードを気軽に買うことに引け目を感じ、禁止になるまでは環境に取り残されて土俵に立つのが難しいという状況に陥ってしまいました。
このような背景があり以前より積極的に新カードや新デッキを試す機会というのが確実に減り、同時にレガシーに向き合う時間も減っていきました。
そんな意図的な特殊セットによるインフレは、残念ながら自分にとってレガシーには望んでいない方向に進んでいます。これが原因でMTGから離れてしまった仲間やプレイヤーも見ました。
自分もそれならばと一瞬よぎりましたが、MTGが趣味として好きな気持ちはどうしても変わらなかったので、やはり無理に追うことはせずに禁止改定によってしっかりと調整が行われた環境に戻った時にまったり楽しんだりたまに大会に出るというスタンスに切り替え、最悪このままインフレの加速状態が変わることがなければ、引退までとはいかずとも大会に出ることはせずこのまま身内だけで楽しむ程度に留めるか、カードを寝かせ休止してしまう事を視野に入れてもいいかなと思っています。
レガシーを通じて気の許せる仲間ができたのも事実です。この仲間がいなければカードやデッキに対する評価や考え方、プレイングは絶対に磨かれることはなかったでしょう。レガシーを楽しむことにおいてこうした仲間の存在が一番のモチベーションになっていたのは間違いありません。
仮にレガシーを休止したとしても仲間との関係は休止するつもりは全くないので、人との繋がりは今までと変わらず大事にしていきたいなと思います。
最後になりますが、今まで自分の日記を見てくださったりコメントしてくださった方々、本当にありがとうございました。
現在レガシーに関する考察等は、変わらずツイッター(@screamo0116)で細々と続けていますので、コメントも大歓迎ですし今後も暖かく見守っていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。
では。
1/26 第124回KMC結果
2020年1月27日 Magic: The Gathering先週テーロスの還魂記も発売され、個人的注目カードも挙げていないぐらい更新が止まってしまう程のサボりっぷりではありますが、水面下では事前の予約や調整自体はコツコツ進めていました。
レガシーではその中でも最も注目度が高いカードといえば、令和のヨグウィルこと死の国からの脱出。LEDやペタル+思考停止と組み合わせることで瞬殺できるコンボデッキが公開から瞬く間に広まりました。
2マナと軽く同じカードを何回でも撃つことができるこれはヨグウィルにない強さで、ポテンシャルはかなり高そうと思い自分もそのコンボの調整に乗り出しました。
UR・ジェスカイ・グリクシス・ティムールと、様々なカラーを試し、サイドメンターを取れるジェスカイか夏の帳を取れるティムールかで悩みに悩み、最終的に今回のKMCではティムールカラーで決定。
そのレシピがこちら。
4水蓮の花びら
4ライオンの瞳のダイアモンド
4渦まく知識
4思案
4定業
3ギャンブル
3発生の器
2呪文貫き
2夏の帳
1狼狽の嵐
4死の国からの脱出
4思考停止
1ぶどう弾
4意志の力
44
2Volcanic Island
1Tropical Island
3島
1山
1森
4沸騰する小湖
4霧深い雨林
16
SB
2沈黙の墓石
2自然への回帰
1夏の帳
1狼狽の嵐
1花の絨毯
1ザンティッドの大群
2厚かましい借り手
1紅蓮地獄
1削剥
1渋面の溶岩使い
2王冠泥棒、オーコ
15
ライブラリーアウトもしくは夏の帳を撃たれると勝てない相手に関しては、追加の勝ち手段としてぶどう弾を採用。最悪ストーム2〜3で素撃ちしてもデスタクなどの厄介な生物に当てられるため腐る場面は少ないと踏みました。
脱出コストを払うために墓地を多く消費するため思考掃きを取っていることが多いですが、個人的には調整中あまりしっくりこなかったので他の選択肢はないかと考えたところ、発生の器に辿り着きました。序盤は2ターンと合計3マナを消費してしまいますが、設置は1マナと軽くて構えられるので隙は小さく、うまくいけばこれ1枚で脱出ハンド+LED墓地送り+思考停止墓地送り+墓地肥やしとコンボパーツ全てにアクセスできる可能性があり、それが決まれば3ターン目にほぼ確実にコンボが決められます。実際はそううまくいきませんが、どれか一つでも噛み合えば御の字で最悪土地をもらうこともできるので悪くありません。
サイド後は確実に墓地対策がキツくなるので、サージカル対策に沈黙の墓石、置物系墓地対策には自然への回帰、対処できなかった時の別の勝ち手段として単体で強いオーコを採用。また、創造者カーンがかなり厳しいので、厚かましい借り手でバウンスと戦闘による破壊を兼ね備えます。
さて、それでは大会の結果です。
今回は参加人数62人の6回戦。
1回戦目:サルベイジャーコンボ ×○○
1Gは先にメンター無限パンプ決められ、2Gはオーコ無双
3G、思考停止を探すも先にメンターからトークンをばら撒かれターンを返せば死ぬところまで来てしまったのでコンボ強制始動。幸い思案から1発で思考停止を引き当てられた
2回戦目:バント石鍛冶 ○○
ゆっくりな相手なのでかなり楽に倒せた。
3回戦目:忍者 ○○
忍術でアドを取られるも、妨害をきっちり抱えて勝ち。
2Gはオーコで時間を稼ぎつつ沈黙の墓石でフェアリーの忌み者を先に使わせる。マナファクトが抜かれたが土地は伸びたのでコンボスタート。墓地にLEDが落ちたため勝ち。
4回戦目:スニークショー ×○×
1Gは母聖樹からスニーク→エムラ。2Gは先にスニークを置かれるがハンドに生物なし。返しに割って時間を稼ぎコンボ→ぶどう弾で勝ち。3Gは先にこちらが動くも相手の方が妨害が多く空振り。返しにスニーク→エムラで置いていた沈黙の墓石もろとも滅殺。ドローゴーが続き職工を置かれるもぶどう弾でなんとか処理と思ったらサージカルで脱出を抜かれジエンド。
5回戦目:感染 ×○×
流石に無理。2Gは先にオーコが着地できたため抑え込めたが速度、妨害共に相手の方が強く相性はかなり悪い。
6回戦目:研磨基地脱出 ○××
2マナランドやアーティファクトを基調とした、一般的なタイプとは違う脱出コンボ。サイド後どちらも黒力線スタートで速度が落ちヘルムコンボでいかれる。特に3Gは思考停止がなかなか来ず力戦を割っても更に出てきてヘルムも2枚来て防戦一方なところに脱出と研磨基地を置かれ終了。
3連勝でこれはいけるかと思いきや痛恨の3連敗で3-3。
トップ8には脱出コンボは残らなかったものの、周りを見渡すと使っている人をかなり見かけたので少し驚き。ただ結果にも出ているように、脱出ストームは強いですがサイド後はどうしても墓地対策に苦しむことになるので、体感としては決して強過ぎるということはないかなと思います。特にメインから墓地対策を取っているスローデプスやマーベリックにはかなりの苦戦を強いられると思うので、サイド後含め別の勝ち手段をもっと充実させる必要があるなと感じました。
今回はティームールカラーでしたが、そう考えると次なる選択肢はやはりメンターの取れるジェスカイが良さそうです。別の勝ち手段として調整によってはメインから入れるのも悪くないかもしれません。
今色んな型が試されている最も旬なデッキの脱出コンボ。形が決まるまではもう少し煮詰める必要がありますがバリエーションは豊富なので、今後も様々な形で見ることになりそうです。
レガシーではその中でも最も注目度が高いカードといえば、令和のヨグウィルこと死の国からの脱出。LEDやペタル+思考停止と組み合わせることで瞬殺できるコンボデッキが公開から瞬く間に広まりました。
2マナと軽く同じカードを何回でも撃つことができるこれはヨグウィルにない強さで、ポテンシャルはかなり高そうと思い自分もそのコンボの調整に乗り出しました。
UR・ジェスカイ・グリクシス・ティムールと、様々なカラーを試し、サイドメンターを取れるジェスカイか夏の帳を取れるティムールかで悩みに悩み、最終的に今回のKMCではティムールカラーで決定。
そのレシピがこちら。
4水蓮の花びら
4ライオンの瞳のダイアモンド
4渦まく知識
4思案
4定業
3ギャンブル
3発生の器
2呪文貫き
2夏の帳
1狼狽の嵐
4死の国からの脱出
4思考停止
1ぶどう弾
4意志の力
44
2Volcanic Island
1Tropical Island
3島
1山
1森
4沸騰する小湖
4霧深い雨林
16
SB
2沈黙の墓石
2自然への回帰
1夏の帳
1狼狽の嵐
1花の絨毯
1ザンティッドの大群
2厚かましい借り手
1紅蓮地獄
1削剥
1渋面の溶岩使い
2王冠泥棒、オーコ
15
ライブラリーアウトもしくは夏の帳を撃たれると勝てない相手に関しては、追加の勝ち手段としてぶどう弾を採用。最悪ストーム2〜3で素撃ちしてもデスタクなどの厄介な生物に当てられるため腐る場面は少ないと踏みました。
脱出コストを払うために墓地を多く消費するため思考掃きを取っていることが多いですが、個人的には調整中あまりしっくりこなかったので他の選択肢はないかと考えたところ、発生の器に辿り着きました。序盤は2ターンと合計3マナを消費してしまいますが、設置は1マナと軽くて構えられるので隙は小さく、うまくいけばこれ1枚で脱出ハンド+LED墓地送り+思考停止墓地送り+墓地肥やしとコンボパーツ全てにアクセスできる可能性があり、それが決まれば3ターン目にほぼ確実にコンボが決められます。実際はそううまくいきませんが、どれか一つでも噛み合えば御の字で最悪土地をもらうこともできるので悪くありません。
サイド後は確実に墓地対策がキツくなるので、サージカル対策に沈黙の墓石、置物系墓地対策には自然への回帰、対処できなかった時の別の勝ち手段として単体で強いオーコを採用。また、創造者カーンがかなり厳しいので、厚かましい借り手でバウンスと戦闘による破壊を兼ね備えます。
さて、それでは大会の結果です。
今回は参加人数62人の6回戦。
1回戦目:サルベイジャーコンボ ×○○
1Gは先にメンター無限パンプ決められ、2Gはオーコ無双
3G、思考停止を探すも先にメンターからトークンをばら撒かれターンを返せば死ぬところまで来てしまったのでコンボ強制始動。幸い思案から1発で思考停止を引き当てられた
2回戦目:バント石鍛冶 ○○
ゆっくりな相手なのでかなり楽に倒せた。
3回戦目:忍者 ○○
忍術でアドを取られるも、妨害をきっちり抱えて勝ち。
2Gはオーコで時間を稼ぎつつ沈黙の墓石でフェアリーの忌み者を先に使わせる。マナファクトが抜かれたが土地は伸びたのでコンボスタート。墓地にLEDが落ちたため勝ち。
4回戦目:スニークショー ×○×
1Gは母聖樹からスニーク→エムラ。2Gは先にスニークを置かれるがハンドに生物なし。返しに割って時間を稼ぎコンボ→ぶどう弾で勝ち。3Gは先にこちらが動くも相手の方が妨害が多く空振り。返しにスニーク→エムラで置いていた沈黙の墓石もろとも滅殺。ドローゴーが続き職工を置かれるもぶどう弾でなんとか処理と思ったらサージカルで脱出を抜かれジエンド。
5回戦目:感染 ×○×
流石に無理。2Gは先にオーコが着地できたため抑え込めたが速度、妨害共に相手の方が強く相性はかなり悪い。
6回戦目:研磨基地脱出 ○××
2マナランドやアーティファクトを基調とした、一般的なタイプとは違う脱出コンボ。サイド後どちらも黒力線スタートで速度が落ちヘルムコンボでいかれる。特に3Gは思考停止がなかなか来ず力戦を割っても更に出てきてヘルムも2枚来て防戦一方なところに脱出と研磨基地を置かれ終了。
3連勝でこれはいけるかと思いきや痛恨の3連敗で3-3。
トップ8には脱出コンボは残らなかったものの、周りを見渡すと使っている人をかなり見かけたので少し驚き。ただ結果にも出ているように、脱出ストームは強いですがサイド後はどうしても墓地対策に苦しむことになるので、体感としては決して強過ぎるということはないかなと思います。特にメインから墓地対策を取っているスローデプスやマーベリックにはかなりの苦戦を強いられると思うので、サイド後含め別の勝ち手段をもっと充実させる必要があるなと感じました。
今回はティームールカラーでしたが、そう考えると次なる選択肢はやはりメンターの取れるジェスカイが良さそうです。別の勝ち手段として調整によってはメインから入れるのも悪くないかもしれません。
今色んな型が試されている最も旬なデッキの脱出コンボ。形が決まるまではもう少し煮詰める必要がありますがバリエーションは豊富なので、今後も様々な形で見ることになりそうです。
12/15 エターナルパーティ2019結果
2019年12月19日 Magic: The Gathering最近めっきり更新が止まってしまいましたが、行ってきました。
今回参加するにあたってレンと六番が禁止になった後ということで、デッキ選択はかなり悩みました。当初はオーコを無視できる墨蛾が使うことができて夏の帳も使える感染(青緑かt白か)で少し調整しましたが、直前でいい感触が全く掴めず断念。
となるとオーコはやはり使う側にしようということで、1年の締め括りとして今年一番調整をしてきた開墾者入りのカナスレでいこうと決意。
レンと六番の禁止で開墾者とのシナジーは薄まりましたがそれでも単体の性能として十分な手応えがあり、オーコという強力なカードのおかげで穴埋めができると思ったので再調整し、以下のレシピに落ち着きました。
4秘密を掘り下げる者
3エルフの開墾者
4タルモゴイフ
11
4渦まく知識
4思案
4稲妻
2呪文貫き
2呪文嵌め
3もみ消し
1輪作
4目くらまし
3王冠泥棒、オーコ
4意志の力
31
3Tropical Island
3Volcanic Island
1蛮族のリング
3不毛の大地
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
18
SB
1イゼットの静電術師
1古の遺恨
1燃え殻蔦
1自然への回帰
1仕組まれた爆薬
2外科的摘出
2紅蓮破
2夏の帳
1冬の宝珠
1森の知恵
1ボジューカの沼
1カラカス
15
輪作をメインから入れて開墾者を早い段階で3/4にしてクロック速度の強化と火力に耐性を付けるようにしました。火力除去やコンバットトリックに使うことができればアド損も解消できます。
オーコ3枚は多めではあると思いますが、直近のメタでバントミラクルなどのコントロールが増えてきているのとミラーマッチを想定した結果本来の2枚から増量しました。
さて今年のエタパですが、参加人数243人の9回戦。
以下が対戦結果です。
1回戦目:アブザンジャンク ××
森知恵や石鍛冶タルモラスアナ等のパワーカードをひたすら叩きつけられ捌けず負け。
2回戦目:RUGペインター ×○○
1Gはライフ3まで追い詰めるもウルザの束の間の開口能力からコンボが完成されてしまい負け。勝ちのゲームは土地を攻めてデルバーやタルモで勝ち。
3回戦目:UGストンピィ ○○
こちらも土地攻めとオーコで座席を鹿にしたりして縛って勝ち。
4回戦目:バントミラクル ○××
除去が途切れずPWで蓋をされて負け。
5回戦目:サルベイジャー ×○×
1Gが完全なやらかしのクソミスプ。相手残りハンドゼロでサルベイジャーキャスト。こちらのハンドはWill目くらましオーコでWill素直にすればいいのに、なぜか場に出ているLEDを無駄に使わせると勘違いして目くらましを撃ってしまう。もちろん相手はLEDからマナを出し支払い。ここで再度Willを使えばまだよかったが、ハンドゼロなので無限マナが出せるだけで終わるので返しでオーコからサルベイジャーを鹿に変えればいいと思いそのまま通してしまうと、ガラクタが墓地にあるのを失念してしまい大量ドローからコンボ決められて負け。本当に情けない。
6回戦目:青白デルバー ○○
相手はオーコを対処できずコントロールして勝ち。
7回戦目:URデルバー(ヤンパイ型) ×○×
1G不毛ハメ食らい負け、2Gは相手デルバーを輪作→蛮族のリングで焼きつつ3/4に成長した開墾者とタルモが硬く、ネメシスに立たれてもお構いなく殴りに行けて勝ち。3G色事故により死。
ここでドロップし、3-4の負け越しで終わりました。
デッキ選択について悔いは一切なくレンと六番がいなくても開墾者の感触は悪くなかったですが、敗因は5回戦目のプレイングこれに尽きます。練習不足で本当下手でした。
結果としては散々な今回の大会でしたが、途中対戦後にツイッターでこのデッキを知ってくれていた人から、「よしおさんですよね、このカラーで開墾者を使ってる人は1人しかいないので」と、デッキビルダー冥利に尽きるとても嬉しいお声をかけていただく機会がありました。
それだけに今回の結果について自分を知ってくれている方には面目を保つことができず不甲斐ない思いでいっぱいで仕方がありません。
ただそうやって知ってくれている人がいるというだけで自分としてはものすごいモチベーションになるので、また新環境になっても自分の構築を信じて、来年こそは面目を保つため自分の構築をもっと多くの人に知ってもらうために調整と練習を頑張りたいと思います。
今回参加するにあたってレンと六番が禁止になった後ということで、デッキ選択はかなり悩みました。当初はオーコを無視できる墨蛾が使うことができて夏の帳も使える感染(青緑かt白か)で少し調整しましたが、直前でいい感触が全く掴めず断念。
となるとオーコはやはり使う側にしようということで、1年の締め括りとして今年一番調整をしてきた開墾者入りのカナスレでいこうと決意。
レンと六番の禁止で開墾者とのシナジーは薄まりましたがそれでも単体の性能として十分な手応えがあり、オーコという強力なカードのおかげで穴埋めができると思ったので再調整し、以下のレシピに落ち着きました。
4秘密を掘り下げる者
3エルフの開墾者
4タルモゴイフ
11
4渦まく知識
4思案
4稲妻
2呪文貫き
2呪文嵌め
3もみ消し
1輪作
4目くらまし
3王冠泥棒、オーコ
4意志の力
31
3Tropical Island
3Volcanic Island
1蛮族のリング
3不毛の大地
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
18
SB
1イゼットの静電術師
1古の遺恨
1燃え殻蔦
1自然への回帰
1仕組まれた爆薬
2外科的摘出
2紅蓮破
2夏の帳
1冬の宝珠
1森の知恵
1ボジューカの沼
1カラカス
15
輪作をメインから入れて開墾者を早い段階で3/4にしてクロック速度の強化と火力に耐性を付けるようにしました。火力除去やコンバットトリックに使うことができればアド損も解消できます。
オーコ3枚は多めではあると思いますが、直近のメタでバントミラクルなどのコントロールが増えてきているのとミラーマッチを想定した結果本来の2枚から増量しました。
さて今年のエタパですが、参加人数243人の9回戦。
以下が対戦結果です。
1回戦目:アブザンジャンク ××
森知恵や石鍛冶タルモラスアナ等のパワーカードをひたすら叩きつけられ捌けず負け。
2回戦目:RUGペインター ×○○
1Gはライフ3まで追い詰めるもウルザの束の間の開口能力からコンボが完成されてしまい負け。勝ちのゲームは土地を攻めてデルバーやタルモで勝ち。
3回戦目:UGストンピィ ○○
こちらも土地攻めとオーコで座席を鹿にしたりして縛って勝ち。
4回戦目:バントミラクル ○××
除去が途切れずPWで蓋をされて負け。
5回戦目:サルベイジャー ×○×
1Gが完全なやらかしのクソミスプ。相手残りハンドゼロでサルベイジャーキャスト。こちらのハンドはWill目くらましオーコでWill素直にすればいいのに、なぜか場に出ているLEDを無駄に使わせると勘違いして目くらましを撃ってしまう。もちろん相手はLEDからマナを出し支払い。ここで再度Willを使えばまだよかったが、ハンドゼロなので無限マナが出せるだけで終わるので返しでオーコからサルベイジャーを鹿に変えればいいと思いそのまま通してしまうと、ガラクタが墓地にあるのを失念してしまい大量ドローからコンボ決められて負け。本当に情けない。
6回戦目:青白デルバー ○○
相手はオーコを対処できずコントロールして勝ち。
7回戦目:URデルバー(ヤンパイ型) ×○×
1G不毛ハメ食らい負け、2Gは相手デルバーを輪作→蛮族のリングで焼きつつ3/4に成長した開墾者とタルモが硬く、ネメシスに立たれてもお構いなく殴りに行けて勝ち。3G色事故により死。
ここでドロップし、3-4の負け越しで終わりました。
デッキ選択について悔いは一切なくレンと六番がいなくても開墾者の感触は悪くなかったですが、敗因は5回戦目のプレイングこれに尽きます。練習不足で本当下手でした。
結果としては散々な今回の大会でしたが、途中対戦後にツイッターでこのデッキを知ってくれていた人から、「よしおさんですよね、このカラーで開墾者を使ってる人は1人しかいないので」と、デッキビルダー冥利に尽きるとても嬉しいお声をかけていただく機会がありました。
それだけに今回の結果について自分を知ってくれている方には面目を保つことができず不甲斐ない思いでいっぱいで仕方がありません。
ただそうやって知ってくれている人がいるというだけで自分としてはものすごいモチベーションになるので、また新環境になっても自分の構築を信じて、来年こそは面目を保つため自分の構築をもっと多くの人に知ってもらうために調整と練習を頑張りたいと思います。
神秘の聖域入り青白相殺奇跡コントロール構築
2019年10月22日 Magic: The Gathering前回の日記でエルドレインの王権の注目カードとして挙げた神秘の聖域ですが、まさに奇跡デッキにとってうってつけのカードと言えます。
奇跡デッキと言えば、コントロールデッキとしての性質上島が並びやすく、マナ基盤安定化のためにフェッチも多用し、終末や相殺のようなライブラリートップを操作することが重要なので、神秘の聖域は中盤以降の奇跡呪文や相殺の積み込みとして非常に相性が良く、そうでなくてもトップ勝負にも連れ込んだときのブレストやソープロ、議会の採決を使い回すだけでもなかなか強力なため、是非ともこれをベースとした構築をしたいところ。
しかし既存の奇跡デッキのレシピに入れるだけでは完全に噛み合っているとは言い難く、例えば基本に帰れと相性が悪いなどで十分なポテンシャルを引き出しているとは言い切れない部分もあります。
ですので今回は、奇跡デッキの強みをそのままに神秘の聖域をいかに有効に活用できるかを考察し、新しい奇跡デッキを構築していきたいと思います。
まず前提として神秘の聖域の能力を使うには島を3枚以上出している必要がありますが、これが実は既存の奇跡デッキにとって意外とネックな部分になっています。
ソープロや終末、中盤以降の議会の採決や至高の評決を撃つために序盤に平地を1〜2枚置かなくてはいけない状況が多々存在するので、そうなると神秘の聖域の能力を使うタイミングが平均すると6〜7ターン目以降となり、ゲーム後半にならないと活用できない可能性が高くなってしまいます。また、平地をサーチするためのフェッチも多数消費してしまうので、せっかく神秘の聖域を入れても「積み込みたい時に積み込めない」という状況に陥りやすくなり、そうなれば神秘の聖域は基本の島以下の使いにくい土地でしかなく本末転倒です。それに神秘の聖域は積み込みとしての利用以外にもサイド後のサージカル回避としても使いたいため、やはりできるだけ早く能力を使いたいところです。
もちろんTundraを置けば島としてもカウントできるので解消するための選択肢ではありますが、不毛の大地の存在がある以上ほとんどの状況では序盤に積極的に出したいものではありません。
そんな既存の奇跡デッキではやや使いにくくなってしまう神秘の聖域のネックな部分を全て解消してくれるのが、アーカムの天測儀です。
アーカムは元々4色デッキやジェスカイカラーのコントロールデッキなど3色以上のマナ基盤安定化のために用いられていますが、ここでは一見大して必要のない2色且つ基本地形が多数入れられている奇跡デッキで敢えてアーカムを利用するというのが今回の構築の1番のポイントです。
もちろんアーカムの基本の役割は色マナ安定化なので、色の違うダブルシンボルを序盤に用意しやすくなるという意味でも奇跡デッキでは十分役には立ちますが、今回の神秘の聖域を活用した奇跡デッキで使用する真の目的は、「序盤に島ばかり並べられる」ことと「フェッチを温存できる」ことです。基本の島しか並べていなくてもアーカムがあればソープロなどの除去を飛ばすことができ、そうすることでフェッチから平地をサーチする回数が減るためフェッチを温存することができ、より神秘の聖域で積み込みたいタイミングでフェッチを使えるということに貢献してくれます。
以上を踏まえた上でそれ以外にも様々なシナジー等を考慮し、完成したレシピがこちらです。
3僧院の導師
3
4思案
4渦まく知識
4アーカムの天測儀
4剣を鋤に
4相殺
2呪文貫き
3任務説明
1ドビンの拒否権
2議会の採決
2精神を刻む者、ジェイス
4意志の力
3終末
37
6冠雪の島
2冠雪の平地
1Tundra
1カラカス
2神秘の聖域
4溢れかえる岸辺
4汚染された三角州
20
※SBは割愛
トップ操作の自由度が上がったことにより、相殺とのシナジーを重視し4枚フル投入。これによりロックはもちろん除去耐性の低いメンターを守りやすくします。
アーカムはハンドを減らさずメンターのトークンを生成してくれるという意味でもこのデッキとは相性抜群。
神秘の聖域の枚数に関しては、複数回使いたい場面は多くありますがやはりハンドには来てほしいカードではないため、残念ながら2枚が限界のようです。
この構築でアーカム以外の重要なポイントとして任務説明を採用しているところです。瞬唱とは違い直接のアドバンテージを稼げませんが、採用にはもちろんそれなりの理由があります。
まず、アーカムのおかげで青ダブシンが手軽に唱えられるようになったのと相殺フル投入のため諜報によるトップ操作のシナジーを重視しているのがひとつ。
次に、神秘の聖域のおかげで終末が奇跡で撃ちやすくなり、瞬唱自身も巻き添えになるためブロッカーとしての役割がそこまで重要にならないという点。
また神秘の聖域と相殺のシナジーを考えた場合、瞬唱だと生物なので墓地から積み込むことができず他の2マナ呪文の枠を必要としてしまうのがネックになりますが、任務説明なら能動的に使って墓地に落とせるので2マナ域の積み込みがしやすくなり、枠も圧迫しません。
後は当然ではありますがメンターのトークン生成が1枚で2回できるというのも理由のひとつ。
枠の関係上もありますがPWは直接の勝ち手段にもなるジェイスのみにしています。3マナテフェリーや3マナナーセットも捨てがたいですが、ここに3マナ域を消費してしまうと、任務説明を採用しているポイントと同じく神秘の聖域でトップに戻せる呪文が少なくなってしまいトップ操作を十分に活用できなくなってしまうのと、相手の行動を制限する手段は相殺が着地すればそれで十分なため、今回は採用を見送りました。
打ち消し呪文に関してですが、相殺を早期に着地させるためや後手からでも序盤のレンと六番やコンボに対抗できるようピアスを2枚取っています。相殺さえ着地させれば妨害手段はなんとかなるので軽さを重視。
1枚挿しのドビンの拒否権は、代わりに対抗呪文かもしくは相殺の3マナ域を増やすのも兼ねて否定の力が有力候補で、この辺りはメタによって調整したいと思っています。
フェッチは全て島か神秘の聖域を持ってこられる土地だけに絞っています。アーカムがあると白マナはこれと溢れかえる岸辺だけでも十分確保できるので、神秘の聖域を持ってこられない虹色の眺望や青を含まない白系フェッチというノイズになりうる土地は採用しなくて済みます。メインでは基本に帰れを入れていないので、デプス対策のお守りとしてカラカスも採用しています。
デッキ構築についてのの大まかな考察や解説は以上です。
個人的にあまり時間のかかるコントロールデッキはあまり好みではなく大会でもほとんど使ったことはありませんが、今回の構築した奇跡デッキは調整したり回してみると面白くかなり気に入ったので、次回の大会は一度これを持ち込んで試してみようかなと思っています。
奇跡デッキと言えば、コントロールデッキとしての性質上島が並びやすく、マナ基盤安定化のためにフェッチも多用し、終末や相殺のようなライブラリートップを操作することが重要なので、神秘の聖域は中盤以降の奇跡呪文や相殺の積み込みとして非常に相性が良く、そうでなくてもトップ勝負にも連れ込んだときのブレストやソープロ、議会の採決を使い回すだけでもなかなか強力なため、是非ともこれをベースとした構築をしたいところ。
しかし既存の奇跡デッキのレシピに入れるだけでは完全に噛み合っているとは言い難く、例えば基本に帰れと相性が悪いなどで十分なポテンシャルを引き出しているとは言い切れない部分もあります。
ですので今回は、奇跡デッキの強みをそのままに神秘の聖域をいかに有効に活用できるかを考察し、新しい奇跡デッキを構築していきたいと思います。
まず前提として神秘の聖域の能力を使うには島を3枚以上出している必要がありますが、これが実は既存の奇跡デッキにとって意外とネックな部分になっています。
ソープロや終末、中盤以降の議会の採決や至高の評決を撃つために序盤に平地を1〜2枚置かなくてはいけない状況が多々存在するので、そうなると神秘の聖域の能力を使うタイミングが平均すると6〜7ターン目以降となり、ゲーム後半にならないと活用できない可能性が高くなってしまいます。また、平地をサーチするためのフェッチも多数消費してしまうので、せっかく神秘の聖域を入れても「積み込みたい時に積み込めない」という状況に陥りやすくなり、そうなれば神秘の聖域は基本の島以下の使いにくい土地でしかなく本末転倒です。それに神秘の聖域は積み込みとしての利用以外にもサイド後のサージカル回避としても使いたいため、やはりできるだけ早く能力を使いたいところです。
もちろんTundraを置けば島としてもカウントできるので解消するための選択肢ではありますが、不毛の大地の存在がある以上ほとんどの状況では序盤に積極的に出したいものではありません。
そんな既存の奇跡デッキではやや使いにくくなってしまう神秘の聖域のネックな部分を全て解消してくれるのが、アーカムの天測儀です。
アーカムは元々4色デッキやジェスカイカラーのコントロールデッキなど3色以上のマナ基盤安定化のために用いられていますが、ここでは一見大して必要のない2色且つ基本地形が多数入れられている奇跡デッキで敢えてアーカムを利用するというのが今回の構築の1番のポイントです。
もちろんアーカムの基本の役割は色マナ安定化なので、色の違うダブルシンボルを序盤に用意しやすくなるという意味でも奇跡デッキでは十分役には立ちますが、今回の神秘の聖域を活用した奇跡デッキで使用する真の目的は、「序盤に島ばかり並べられる」ことと「フェッチを温存できる」ことです。基本の島しか並べていなくてもアーカムがあればソープロなどの除去を飛ばすことができ、そうすることでフェッチから平地をサーチする回数が減るためフェッチを温存することができ、より神秘の聖域で積み込みたいタイミングでフェッチを使えるということに貢献してくれます。
以上を踏まえた上でそれ以外にも様々なシナジー等を考慮し、完成したレシピがこちらです。
3僧院の導師
3
4思案
4渦まく知識
4アーカムの天測儀
4剣を鋤に
4相殺
2呪文貫き
3任務説明
1ドビンの拒否権
2議会の採決
2精神を刻む者、ジェイス
4意志の力
3終末
37
6冠雪の島
2冠雪の平地
1Tundra
1カラカス
2神秘の聖域
4溢れかえる岸辺
4汚染された三角州
20
※SBは割愛
トップ操作の自由度が上がったことにより、相殺とのシナジーを重視し4枚フル投入。これによりロックはもちろん除去耐性の低いメンターを守りやすくします。
アーカムはハンドを減らさずメンターのトークンを生成してくれるという意味でもこのデッキとは相性抜群。
神秘の聖域の枚数に関しては、複数回使いたい場面は多くありますがやはりハンドには来てほしいカードではないため、残念ながら2枚が限界のようです。
この構築でアーカム以外の重要なポイントとして任務説明を採用しているところです。瞬唱とは違い直接のアドバンテージを稼げませんが、採用にはもちろんそれなりの理由があります。
まず、アーカムのおかげで青ダブシンが手軽に唱えられるようになったのと相殺フル投入のため諜報によるトップ操作のシナジーを重視しているのがひとつ。
次に、神秘の聖域のおかげで終末が奇跡で撃ちやすくなり、瞬唱自身も巻き添えになるためブロッカーとしての役割がそこまで重要にならないという点。
また神秘の聖域と相殺のシナジーを考えた場合、瞬唱だと生物なので墓地から積み込むことができず他の2マナ呪文の枠を必要としてしまうのがネックになりますが、任務説明なら能動的に使って墓地に落とせるので2マナ域の積み込みがしやすくなり、枠も圧迫しません。
後は当然ではありますがメンターのトークン生成が1枚で2回できるというのも理由のひとつ。
枠の関係上もありますがPWは直接の勝ち手段にもなるジェイスのみにしています。3マナテフェリーや3マナナーセットも捨てがたいですが、ここに3マナ域を消費してしまうと、任務説明を採用しているポイントと同じく神秘の聖域でトップに戻せる呪文が少なくなってしまいトップ操作を十分に活用できなくなってしまうのと、相手の行動を制限する手段は相殺が着地すればそれで十分なため、今回は採用を見送りました。
打ち消し呪文に関してですが、相殺を早期に着地させるためや後手からでも序盤のレンと六番やコンボに対抗できるようピアスを2枚取っています。相殺さえ着地させれば妨害手段はなんとかなるので軽さを重視。
1枚挿しのドビンの拒否権は、代わりに対抗呪文かもしくは相殺の3マナ域を増やすのも兼ねて否定の力が有力候補で、この辺りはメタによって調整したいと思っています。
フェッチは全て島か神秘の聖域を持ってこられる土地だけに絞っています。アーカムがあると白マナはこれと溢れかえる岸辺だけでも十分確保できるので、神秘の聖域を持ってこられない虹色の眺望や青を含まない白系フェッチというノイズになりうる土地は採用しなくて済みます。メインでは基本に帰れを入れていないので、デプス対策のお守りとしてカラカスも採用しています。
デッキ構築についてのの大まかな考察や解説は以上です。
個人的にあまり時間のかかるコントロールデッキはあまり好みではなく大会でもほとんど使ったことはありませんが、今回の構築した奇跡デッキは調整したり回してみると面白くかなり気に入ったので、次回の大会は一度これを持ち込んで試してみようかなと思っています。
前回の続きです。今回はこれでラストとなります。
13、王冠泥棒、オーコ
まず3マナと軽いのに初期忠誠度4で+2能力を持つので、なんと言っても硬いのが特徴。
+2の食物トークン自体は食物シナジーがないと盤面には影響がないが、単純に3ライフゲインを連発できるだけで本体の硬さも相まってビート系からしたら悶絶もの。
盤面に触れる+1は直接アドは取らないが、リアニ生物やグリセル・エムラのようなファッティだけでなくチャリスや三球、罠橋のような厄介な置物までも3/3バニラに変えてしまうので、楽々除去や戦闘で処理しやすく間接的なアドに繋がりやすい。
-5の奥義はやや控えめなものの、一度プラスすれば到達できる上にこちらは基本的に自身で出した食物を送りつければいいだけ。こちらがもらえるのはパワーが3以下の生物限定なので、レガシーではデルバー、ヤンパイ、秘儀術師、石鍛冶、ボブ、デスタクの生物全般辺りが候補。コントロールの交換でこちらのアーティファクトか生物に制限はないので、コントロールしているとデメリットのあるものを相手に送りつけるというのもひとつの手。
単体では十分な強さがあるので、あとはどういうデッキで使えばいいかが課題となる。白や黒を足せばこれの能力に頼らなくても大型生物を処理できるので、ここはティムールカラーで苦手とする大型生物の処理を兼ねるという使い方が良さそう。ただカナスレでは少々重くレンと六番が既に枠を取っているのでサイド候補になるぐらいだが、ミッドレンジのような中速やコントロール寄りのデッキでうまく組めないか思案中。
14、石とぐろの海蛇
マナレシオ1でXマナを要求する生物もここまでメリット能力を持っていると流石に可能性を感じざるを得ない。ポストやMUDのようなデッキで基本はX=4で唱えることとなる。そうすることで稲妻で落ちず、序盤のデルバーをキャッチしたり、大梟やコアトル、ネメシスを悠々と突破することができる。
15、魔女のかまど
能力自体は1ターンに1回生物を犠牲にして食物トークンを出すだけの地味な効果だが、ゾンバードメントでは基本的にサクり台ありきの動きをするので1ターン目に設置できるというのが重要。2マナ以上のサクり台だと効果が強い反面遅かったり妨害されやすいので、大いなるガルガドンのように保険で軽いこれでサクり台を増量し確実に設置できるようにすれば追放除去も怖くなくなる。
16、ロークスワイン城
POXのようなデッキのアドバンテージ源として使ってみたい。沼を多く取るデッキなのでアンタップインしやすく単体でも黒マナが出るのでマナシンボルのきついデッキではありがたい。他にもヴェリアナと併用すればハンド0からドローしてライフロスを最小限に抑えられるなどデッキとの相性は良好。
17、ドワーフの鉱山
赤単バーンならマナフラ受けにもなり相手よりどうにかして1点でも多く先に与えたいので、1〜2枚入れてライフレースの攻防や詰めの場面で利用したい。山なので中盤以降サーチができて、きっちり火炎破の餌にもなる。
18、神秘の聖域
奇跡デッキとすこぶる相性のいいカード。中盤以降島が並べばフェッチから奇跡呪文を使い回したり相殺のトップ操作を行える。単純にソープロやブレストを使い回すだけでも悪くない。これを入れることで基本に帰れとの相性が悪くなってしまうが、サイド用として割り切りメインはシナジーを重視するのがいいかもしれない。
19、魔女の小屋
黒ストンピィで1枚挿しておけば、こちらもフェッチから中盤の息切れを防ぐのに貢献しそう。アーボーグがあれば4ターン目以降フェッチから確実に能力を活かすことができるし、フェッチを切るタイミングも調節できるのがいい。
13、王冠泥棒、オーコ
まず3マナと軽いのに初期忠誠度4で+2能力を持つので、なんと言っても硬いのが特徴。
+2の食物トークン自体は食物シナジーがないと盤面には影響がないが、単純に3ライフゲインを連発できるだけで本体の硬さも相まってビート系からしたら悶絶もの。
盤面に触れる+1は直接アドは取らないが、リアニ生物やグリセル・エムラのようなファッティだけでなくチャリスや三球、罠橋のような厄介な置物までも3/3バニラに変えてしまうので、楽々除去や戦闘で処理しやすく間接的なアドに繋がりやすい。
-5の奥義はやや控えめなものの、一度プラスすれば到達できる上にこちらは基本的に自身で出した食物を送りつければいいだけ。こちらがもらえるのはパワーが3以下の生物限定なので、レガシーではデルバー、ヤンパイ、秘儀術師、石鍛冶、ボブ、デスタクの生物全般辺りが候補。コントロールの交換でこちらのアーティファクトか生物に制限はないので、コントロールしているとデメリットのあるものを相手に送りつけるというのもひとつの手。
単体では十分な強さがあるので、あとはどういうデッキで使えばいいかが課題となる。白や黒を足せばこれの能力に頼らなくても大型生物を処理できるので、ここはティムールカラーで苦手とする大型生物の処理を兼ねるという使い方が良さそう。ただカナスレでは少々重くレンと六番が既に枠を取っているのでサイド候補になるぐらいだが、ミッドレンジのような中速やコントロール寄りのデッキでうまく組めないか思案中。
14、石とぐろの海蛇
マナレシオ1でXマナを要求する生物もここまでメリット能力を持っていると流石に可能性を感じざるを得ない。ポストやMUDのようなデッキで基本はX=4で唱えることとなる。そうすることで稲妻で落ちず、序盤のデルバーをキャッチしたり、大梟やコアトル、ネメシスを悠々と突破することができる。
15、魔女のかまど
能力自体は1ターンに1回生物を犠牲にして食物トークンを出すだけの地味な効果だが、ゾンバードメントでは基本的にサクり台ありきの動きをするので1ターン目に設置できるというのが重要。2マナ以上のサクり台だと効果が強い反面遅かったり妨害されやすいので、大いなるガルガドンのように保険で軽いこれでサクり台を増量し確実に設置できるようにすれば追放除去も怖くなくなる。
16、ロークスワイン城
POXのようなデッキのアドバンテージ源として使ってみたい。沼を多く取るデッキなのでアンタップインしやすく単体でも黒マナが出るのでマナシンボルのきついデッキではありがたい。他にもヴェリアナと併用すればハンド0からドローしてライフロスを最小限に抑えられるなどデッキとの相性は良好。
17、ドワーフの鉱山
赤単バーンならマナフラ受けにもなり相手よりどうにかして1点でも多く先に与えたいので、1〜2枚入れてライフレースの攻防や詰めの場面で利用したい。山なので中盤以降サーチができて、きっちり火炎破の餌にもなる。
18、神秘の聖域
奇跡デッキとすこぶる相性のいいカード。中盤以降島が並べばフェッチから奇跡呪文を使い回したり相殺のトップ操作を行える。単純にソープロやブレストを使い回すだけでも悪くない。これを入れることで基本に帰れとの相性が悪くなってしまうが、サイド用として割り切りメインはシナジーを重視するのがいいかもしれない。
19、魔女の小屋
黒ストンピィで1枚挿しておけば、こちらもフェッチから中盤の息切れを防ぐのに貢献しそう。アーボーグがあれば4ターン目以降フェッチから確実に能力を活かすことができるし、フェッチを切るタイミングも調節できるのがいい。
前回の続きです。
7、カタカタ橋のトロール
高いマナレシオと能力がどこか冒涜の悪魔を彷彿とさせる生物。
0/1と非力なもののトークンを3体も相手に与えてしまうので最低でも3回は攻撃を無効化されてしまうがその分ライフ3点とドローに変換してくれるので、黒ストンピィでは古えの墳墓のライフロスを補いつつ消耗の激しいハンドを補ってくれるのは決して悪い交換ではない。しかもそのヤギトークンも、自然と併用できる疫病を仕組む者や毒の濁流などで簡単に一掃できるので大したデメリットにもならない。
自身は5マナなのでLake of the Deadと併用するのもアリ。ストンピィでもアーボーグのおかげでサクる沼にはさほど困ることもないだろう。
8、願い爪のタリスマン
アーティファクトになったチューター。出したターンに使ってもシングル3マナなので本家Grim Tutorと比べてもライフロスがないのも考慮して使いやすくなった。
問題は起動後相手に渡してしまうというデメリット。そこをどう解消するかがカギとなるが、これ単体でデメリットを解消する一番の方法はコンボデッキサーチカードとして使ってそのターン中に勝利してしまうこと。そうすれば相手に使われる心配もない。ストーム系のデッキや黒をタッチしたオムニテルに入れるのが有力か。
他のカードで解消するのであれば、大いなる創造者カーンや夢を引き裂く者、アショクで使えなくしたり、ダク・フェイデンなどのコントロール奪取や時を解す者、テフェリーなどのバウンスで再利用する、もしくはリアニでイオナを釣って相手の対抗手段を封じてしまえば実質使われないなど方法は色々あるが、妨害されるなどして失敗した場合は手痛い反撃を受けてしまうので慎重に扱いたい。
9、砕骨の巨人/踏みつけ
生物本体は3マナ4/3メリット能力持ちの時点で十分な性能なのに出来事で2マナの高性能な単体火力が付いているので抜群のコストパフォーマンスを誇る。踏みつけは2マナなのでチャリスにも引っかからず生物本体は2マナランドから唱えられるシングルシンボルのため、ドラゴンストンピィに入れてくださいと言わんばかりでのカードある。枠の関係上なかなか取ることができなかった単体火力をこれのおかげで複数枚取ることができ小回りも効くようになった。
踏みつけの軽減できない能力はネメシスの蔓延るレガシー環境で特に重要。チャンプアタックと見せかけてブロックを誘ってから撃つことでプロテクションを無効化し葬れるので、相手は今後ネメシスで気軽にブロックできないようになる。間接的ではあるがこれで黒や白を使わなくてもネメシスに対処できるようになったので、ストンピィのみならずカナスレやURデルバーのようなフェアデッキでもお呼びがかかる可能性も大いにありうる。
10、探索する獣
4マナ4/4でこれでもかという程のメリット能力を詰め込んだ超インフレ生物。速攻を持つので火力以外の除去耐性のなさもある程度カバーできている。もはやここまでくれば伝説などデメリットと言えないぐらい些細なもの。
ビート系・コントロール系のどちらにも強く、これもまたネメシス対策になりうるカードなので、マーベリックや緑ストンピィ、アグロロームのような4〜5マナ域まで伸びるデッキであれば十分採用されるだろう。
11、湖での水難
相手の墓地に依存するがレガシーは墓地が溜まるデッキが多いので、1〜2枚挿し程度であれば汎用性の高さを十分活かせられる。エスパーやグリコンで試してみたい。ただ探査生物に対しては実質除去も打ち消しも当てられないというのが残念なところ。
12、型破りな協力
青い苦花とも言えるカード。ライフロス以外の部分で本家との差をつけるためにできるだけ相手のターンに2枚以上引きたいがブレスト以外ではなかなか実用的なものはないのが難点。あまり無理せず自分のターンに確実に2枚以上引けるよう、森の知恵などの軽い置物を利用してトークン生成していきたい。迷宮の霊魂や覆いを割くもの、ナーセットが天敵。
7、カタカタ橋のトロール
高いマナレシオと能力がどこか冒涜の悪魔を彷彿とさせる生物。
0/1と非力なもののトークンを3体も相手に与えてしまうので最低でも3回は攻撃を無効化されてしまうがその分ライフ3点とドローに変換してくれるので、黒ストンピィでは古えの墳墓のライフロスを補いつつ消耗の激しいハンドを補ってくれるのは決して悪い交換ではない。しかもそのヤギトークンも、自然と併用できる疫病を仕組む者や毒の濁流などで簡単に一掃できるので大したデメリットにもならない。
自身は5マナなのでLake of the Deadと併用するのもアリ。ストンピィでもアーボーグのおかげでサクる沼にはさほど困ることもないだろう。
8、願い爪のタリスマン
アーティファクトになったチューター。出したターンに使ってもシングル3マナなので本家Grim Tutorと比べてもライフロスがないのも考慮して使いやすくなった。
問題は起動後相手に渡してしまうというデメリット。そこをどう解消するかがカギとなるが、これ単体でデメリットを解消する一番の方法はコンボデッキサーチカードとして使ってそのターン中に勝利してしまうこと。そうすれば相手に使われる心配もない。ストーム系のデッキや黒をタッチしたオムニテルに入れるのが有力か。
他のカードで解消するのであれば、大いなる創造者カーンや夢を引き裂く者、アショクで使えなくしたり、ダク・フェイデンなどのコントロール奪取や時を解す者、テフェリーなどのバウンスで再利用する、もしくはリアニでイオナを釣って相手の対抗手段を封じてしまえば実質使われないなど方法は色々あるが、妨害されるなどして失敗した場合は手痛い反撃を受けてしまうので慎重に扱いたい。
9、砕骨の巨人/踏みつけ
生物本体は3マナ4/3メリット能力持ちの時点で十分な性能なのに出来事で2マナの高性能な単体火力が付いているので抜群のコストパフォーマンスを誇る。踏みつけは2マナなのでチャリスにも引っかからず生物本体は2マナランドから唱えられるシングルシンボルのため、ドラゴンストンピィに入れてくださいと言わんばかりでのカードある。枠の関係上なかなか取ることができなかった単体火力をこれのおかげで複数枚取ることができ小回りも効くようになった。
踏みつけの軽減できない能力はネメシスの蔓延るレガシー環境で特に重要。チャンプアタックと見せかけてブロックを誘ってから撃つことでプロテクションを無効化し葬れるので、相手は今後ネメシスで気軽にブロックできないようになる。間接的ではあるがこれで黒や白を使わなくてもネメシスに対処できるようになったので、ストンピィのみならずカナスレやURデルバーのようなフェアデッキでもお呼びがかかる可能性も大いにありうる。
10、探索する獣
4マナ4/4でこれでもかという程のメリット能力を詰め込んだ超インフレ生物。速攻を持つので火力以外の除去耐性のなさもある程度カバーできている。もはやここまでくれば伝説などデメリットと言えないぐらい些細なもの。
ビート系・コントロール系のどちらにも強く、これもまたネメシス対策になりうるカードなので、マーベリックや緑ストンピィ、アグロロームのような4〜5マナ域まで伸びるデッキであれば十分採用されるだろう。
11、湖での水難
相手の墓地に依存するがレガシーは墓地が溜まるデッキが多いので、1〜2枚挿し程度であれば汎用性の高さを十分活かせられる。エスパーやグリコンで試してみたい。ただ探査生物に対しては実質除去も打ち消しも当てられないというのが残念なところ。
12、型破りな協力
青い苦花とも言えるカード。ライフロス以外の部分で本家との差をつけるためにできるだけ相手のターンに2枚以上引きたいがブレスト以外ではなかなか実用的なものはないのが難点。あまり無理せず自分のターンに確実に2枚以上引けるよう、森の知恵などの軽い置物を利用してトークン生成していきたい。迷宮の霊魂や覆いを割くもの、ナーセットが天敵。
エルドレインの王権のスポイラーが全部出揃いました。
一部では塩セットと言われているようですが、一通り目を通してみるとアドバンテージに直結する出来事や基本地形タイプを持った土地など面白いカードが多く個人的にはなかなかの良セットだなと思っております。
今回も数が多いので3回に分けて早速挙げていきたいと思います。
1、魅力的な王子
主に3番目の能力をアテに採用することになるが、より範囲の広いちらつき鬼火の能力も相手によって腐ることも考えると、1番目と2番目も持っていることで腐ることがなく性能も地味ながら悪くない。
人間デッキに入れて、除去回避はもちろんサリアの副官や反射魔道士、帝国の徴募兵の使い回したい。
2、耳の痛い静寂
たった1マナでストーム系やチェインコンボを封じられる。後手ならサリアやヘイトベアーでは間に合わない可能性もあるのでコンボ対策として非常に強力。デスタクやマーベリックのサイド候補に。
3、群れの番人/安全への導き
出来事で救出を内蔵した生物。生物部分は3/1バニラなのは物足りないが、パーマネントを守れるので霊気の薬瓶やサイドから入れた置物を守れる。こちらも基本は人間デッキで除去回避やcipの使い回しとして使いたい。
4、湖に潜む者、エムリー
墓地からアーティファクトを置ける能力とそのP/Tから、青いゴブリンの技師とも言えそうな生物。自ら墓地を肥やせるのと水蓮の花びらのような墓地に置きやすい物と併用すれば能力を腐らせてしまう可能性も非常に低い。また、唱えられるというのも重要で、練達飛行機械職人、サイの能力も誘発させられるのは大きい。
更に親和アーティファクトと同じコスト軽減能力を持つので、青1マナで唱えることができるのが強く、モックス等を利用して1ターン目から出すことも容易でチャリスと併用してもディスシナジーにならなずサイのサクり能力と相性が良いので、アンティキティーストンピィで使いたい。もしくは青単ペインターでコンボパーツを揃えるために使うのも面白そう。
5、神秘の論争
色対策カードサイクルの中でもずば抜けて強い1枚。赤を取らなくても紅蓮破のような使い勝手を手に入れることができるので、3色目をできるだけ取りたくない奇跡デッキや石鍛冶にとって朗報と言える。更に青くない呪文に対しても3マナ払えばマナ漏出と同じで丸く、メインでタッチされている否定の力と似た使い勝手になりそうなので、レガシーではサイドのみならず代わりにこれをメインに入れるのも悪くない選択肢かもしれない。青単ペインターなら尚更メインから積極的に採用できる。
6、魔法の井戸
序盤はドロー操作やトップ操作として使いつつマナが伸びて隙ができればアドを取りに行くことができるので、奇跡デッキで先触れや定業の枠をこれに変えて試してみたい。序盤にハンドが減るのは少々痛手ではあるが、アドバンテージとトップ操作の両方を兼ね備えているため予報や蓄積した知識の枠を空けることに貢献できるメリットがある。
アーティファクトというのを利用してこのカードも青単ペインターで湖に潜む者、エムリーともぜひ併用したい。
一部では塩セットと言われているようですが、一通り目を通してみるとアドバンテージに直結する出来事や基本地形タイプを持った土地など面白いカードが多く個人的にはなかなかの良セットだなと思っております。
今回も数が多いので3回に分けて早速挙げていきたいと思います。
1、魅力的な王子
主に3番目の能力をアテに採用することになるが、より範囲の広いちらつき鬼火の能力も相手によって腐ることも考えると、1番目と2番目も持っていることで腐ることがなく性能も地味ながら悪くない。
人間デッキに入れて、除去回避はもちろんサリアの副官や反射魔道士、帝国の徴募兵の使い回したい。
2、耳の痛い静寂
たった1マナでストーム系やチェインコンボを封じられる。後手ならサリアやヘイトベアーでは間に合わない可能性もあるのでコンボ対策として非常に強力。デスタクやマーベリックのサイド候補に。
3、群れの番人/安全への導き
出来事で救出を内蔵した生物。生物部分は3/1バニラなのは物足りないが、パーマネントを守れるので霊気の薬瓶やサイドから入れた置物を守れる。こちらも基本は人間デッキで除去回避やcipの使い回しとして使いたい。
4、湖に潜む者、エムリー
墓地からアーティファクトを置ける能力とそのP/Tから、青いゴブリンの技師とも言えそうな生物。自ら墓地を肥やせるのと水蓮の花びらのような墓地に置きやすい物と併用すれば能力を腐らせてしまう可能性も非常に低い。また、唱えられるというのも重要で、練達飛行機械職人、サイの能力も誘発させられるのは大きい。
更に親和アーティファクトと同じコスト軽減能力を持つので、青1マナで唱えることができるのが強く、モックス等を利用して1ターン目から出すことも容易でチャリスと併用してもディスシナジーにならなずサイのサクり能力と相性が良いので、アンティキティーストンピィで使いたい。もしくは青単ペインターでコンボパーツを揃えるために使うのも面白そう。
5、神秘の論争
色対策カードサイクルの中でもずば抜けて強い1枚。赤を取らなくても紅蓮破のような使い勝手を手に入れることができるので、3色目をできるだけ取りたくない奇跡デッキや石鍛冶にとって朗報と言える。更に青くない呪文に対しても3マナ払えばマナ漏出と同じで丸く、メインでタッチされている否定の力と似た使い勝手になりそうなので、レガシーではサイドのみならず代わりにこれをメインに入れるのも悪くない選択肢かもしれない。青単ペインターなら尚更メインから積極的に採用できる。
6、魔法の井戸
序盤はドロー操作やトップ操作として使いつつマナが伸びて隙ができればアドを取りに行くことができるので、奇跡デッキで先触れや定業の枠をこれに変えて試してみたい。序盤にハンドが減るのは少々痛手ではあるが、アドバンテージとトップ操作の両方を兼ね備えているため予報や蓄積した知識の枠を空けることに貢献できるメリットがある。
アーティファクトというのを利用してこのカードも青単ペインターで湖に潜む者、エムリーともぜひ併用したい。
7/28 第113回KMC結果
2019年7月30日 Magic: The Gathering参加人数107人の7回戦。
デッキは前回の日記で構築したエルフの開墾者を入れたRUGデルバーです。今回の大会までに調整を加えたので、まずはレシピを載せたいと思います。
4秘密を掘り下げるもの
4エルフの開墾者
2タルモゴイフ
2真の名の宿敵
12
4渦まく知識
4思案
4稲妻
3もみ消し
2呪文貫き
2呪文嵌め
3レンと六番
4目くらまし
4意志の力
30
3Tropical Island
2Volcanic Island
1焦熱島嶼域
1蛮族のリング
3不毛の大地
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
18
SB
1活性の力
2燃え殻蔦
1四肢切断
1イゼットの静電術師
1外科的摘出
1墓掘りの檻
2紅蓮破
1水流破
1狼狽の嵐
1冬の宝珠
1ボジューカの沼
1カラカス
1幽霊街
15
前回のレシピと違うところは、エルフの開墾者のサーチの幅を広げるために蛮族のリングを採用したところと、そのサーチした土地の使い回しを重視してレンと六番を3枚に増量したところです。デルバーデッキにおいて不毛は基本的に減らしたくはないですが、エルフの開墾者でサーチは可能なのとメタ的にも当然不毛ハメを意識した基本地形の多いデッキが増えてくると読み、3枚に減らしても問題ないと判断して挑みました。
余談ですが、マングースは取っていませんが蛮族のリングがスレッショルド要素を持っているので、デッキは一応カナスレと呼ぶようにしています。
1回戦目:土地単 ○○
1Gは相手溶鉄の渦を着地させてしまうもそのあとのギャンブルをWillできたので動きが止まり、その間に開墾者で墓地を肥やしつつ不毛を構えてレン着地させ殴り勝ち。
2Gはロームをサージカルで抜きつつ土地をのばし開墾者で2枚目の不毛をサーチし動けなくして、罰火圏外の開墾者でコツコツ殴り勝ち。
ちなみに相手もメインから?エルフの開墾者を投入していた。
2回戦目:エルフ ○×○
相手はタフ1ばかりなのでレンと六番が刺さる。更に開墾者から蛮族のリングをサーチさせてレンで使い回し除去が尽きず息切れさせて勝ち。
3回戦目:感染 ○○
このマッチも相手がタフ1だらけなのでレンを着地させると相手はなかなか動けない。墨蛾は厄介なので輪作はきっちり打ち消し、素引きの墨蛾に対しては開墾者からの不毛サーチで対処。
4回戦目:バーン ××
無理。レンは役に立たず相手は舞台照らし入りだったためアド差まで付けられてライフレースが全く間に合わず。
5回戦目:赤MUD ○×○
1Gは相手の先手1Tチャリスからの罠橋まで置かれたが、レンが着地すると不毛ハメ&魂窟からの溶接工は除去で動きを止め、土地を止めたら相手はハンドが溜まるので今度は焦熱島嶼域ドローに切り替えネメシスを探し当てて殴り切ることができた。
2Gはデルバーが全く変身せずその間に磁石のゴーレムを連打され動けず負け。
3Gは打ち消しと不毛ハメで勝ち。
6回戦目:スニークショー ○○
1Gはスニークからのグリセルが間に合い7ドローされてしまうもエムラが引けず、こちらは3/4開墾者2体で相手のライフを詰めていたため、相手2体目のグリセルはブロックに回し悩んだ挙句の7ドローが稲妻圏内に入り対応で稲妻が通り勝ち。
2Gはデルバーが紅蓮破で除去られるも燃え殻蔦が通りガシガシライフを削ってくれる。打ち消しを構えながら追加のクロックを出して、相手は回答を探せずそのまま勝ち。
7回戦目:青白石鍛冶 ○××
1Gはネメシス石鍛冶十手として装備パンチまでされたが、もみ消しで十手のカウンター乗せを阻止しつつ開墾者から蛮族のリングをサーチ。返しにこちらの開墾者ネメシス稲妻蛮族のリングで相手のライフ残り11点をぴったり削り切り。
2Gと3Gは序盤捌き合いになりこちらは中盤以降土地しか引けず捲られ負け。
ということで結果は5-2の惜しくも11位でした。
レンと六番はやはり強かったですが、エルフの開墾者がクロックとしてもシステム生物としても大活躍。蛮族のリングも正解でした。
残念ながら最終戦を落としてしまったためトップ8に残ることはできませんでしたが、エルフの開墾者に関しては十分な手応えを得られて、結果もそれなりに残せたのではないかなと思います。
今回はデルバーのミラーマッチがなかったため不毛は3でもあまり不自由を感じませんでしたが、当たり方によってはやはり4枚欲しい場面も出てくると思います。しかし土地はこれ以上削る枠がなく、もみ消しがかなり枠を圧迫してしまっているので、土地を19枚にしてもみ消しを削るという選択肢も検討中。次回こそトップ8を目指します。
デッキは前回の日記で構築したエルフの開墾者を入れたRUGデルバーです。今回の大会までに調整を加えたので、まずはレシピを載せたいと思います。
4秘密を掘り下げるもの
4エルフの開墾者
2タルモゴイフ
2真の名の宿敵
12
4渦まく知識
4思案
4稲妻
3もみ消し
2呪文貫き
2呪文嵌め
3レンと六番
4目くらまし
4意志の力
30
3Tropical Island
2Volcanic Island
1焦熱島嶼域
1蛮族のリング
3不毛の大地
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
18
SB
1活性の力
2燃え殻蔦
1四肢切断
1イゼットの静電術師
1外科的摘出
1墓掘りの檻
2紅蓮破
1水流破
1狼狽の嵐
1冬の宝珠
1ボジューカの沼
1カラカス
1幽霊街
15
前回のレシピと違うところは、エルフの開墾者のサーチの幅を広げるために蛮族のリングを採用したところと、そのサーチした土地の使い回しを重視してレンと六番を3枚に増量したところです。デルバーデッキにおいて不毛は基本的に減らしたくはないですが、エルフの開墾者でサーチは可能なのとメタ的にも当然不毛ハメを意識した基本地形の多いデッキが増えてくると読み、3枚に減らしても問題ないと判断して挑みました。
余談ですが、マングースは取っていませんが蛮族のリングがスレッショルド要素を持っているので、デッキは一応カナスレと呼ぶようにしています。
1回戦目:土地単 ○○
1Gは相手溶鉄の渦を着地させてしまうもそのあとのギャンブルをWillできたので動きが止まり、その間に開墾者で墓地を肥やしつつ不毛を構えてレン着地させ殴り勝ち。
2Gはロームをサージカルで抜きつつ土地をのばし開墾者で2枚目の不毛をサーチし動けなくして、罰火圏外の開墾者でコツコツ殴り勝ち。
ちなみに相手もメインから?エルフの開墾者を投入していた。
2回戦目:エルフ ○×○
相手はタフ1ばかりなのでレンと六番が刺さる。更に開墾者から蛮族のリングをサーチさせてレンで使い回し除去が尽きず息切れさせて勝ち。
3回戦目:感染 ○○
このマッチも相手がタフ1だらけなのでレンを着地させると相手はなかなか動けない。墨蛾は厄介なので輪作はきっちり打ち消し、素引きの墨蛾に対しては開墾者からの不毛サーチで対処。
4回戦目:バーン ××
無理。レンは役に立たず相手は舞台照らし入りだったためアド差まで付けられてライフレースが全く間に合わず。
5回戦目:赤MUD ○×○
1Gは相手の先手1Tチャリスからの罠橋まで置かれたが、レンが着地すると不毛ハメ&魂窟からの溶接工は除去で動きを止め、土地を止めたら相手はハンドが溜まるので今度は焦熱島嶼域ドローに切り替えネメシスを探し当てて殴り切ることができた。
2Gはデルバーが全く変身せずその間に磁石のゴーレムを連打され動けず負け。
3Gは打ち消しと不毛ハメで勝ち。
6回戦目:スニークショー ○○
1Gはスニークからのグリセルが間に合い7ドローされてしまうもエムラが引けず、こちらは3/4開墾者2体で相手のライフを詰めていたため、相手2体目のグリセルはブロックに回し悩んだ挙句の7ドローが稲妻圏内に入り対応で稲妻が通り勝ち。
2Gはデルバーが紅蓮破で除去られるも燃え殻蔦が通りガシガシライフを削ってくれる。打ち消しを構えながら追加のクロックを出して、相手は回答を探せずそのまま勝ち。
7回戦目:青白石鍛冶 ○××
1Gはネメシス石鍛冶十手として装備パンチまでされたが、もみ消しで十手のカウンター乗せを阻止しつつ開墾者から蛮族のリングをサーチ。返しにこちらの開墾者ネメシス稲妻蛮族のリングで相手のライフ残り11点をぴったり削り切り。
2Gと3Gは序盤捌き合いになりこちらは中盤以降土地しか引けず捲られ負け。
ということで結果は5-2の惜しくも11位でした。
レンと六番はやはり強かったですが、エルフの開墾者がクロックとしてもシステム生物としても大活躍。蛮族のリングも正解でした。
残念ながら最終戦を落としてしまったためトップ8に残ることはできませんでしたが、エルフの開墾者に関しては十分な手応えを得られて、結果もそれなりに残せたのではないかなと思います。
今回はデルバーのミラーマッチがなかったため不毛は3でもあまり不自由を感じませんでしたが、当たり方によってはやはり4枚欲しい場面も出てくると思います。しかし土地はこれ以上削る枠がなく、もみ消しがかなり枠を圧迫してしまっているので、土地を19枚にしてもみ消しを削るという選択肢も検討中。次回こそトップ8を目指します。
エルフの開墾者入りRUGデルバー構築
2019年7月13日 Magic: The Gathering先日の注目カードに挙げていたエルフの開墾者。早速カナスレのマングース枠に入れ替えて回してみましたので今回は使用感と構築、調整について書いていきたいと思います。
まず結論から言えば、想定通りレガシーでも十分に使えるカードパワーを持っていると感じました。クロックを刻めるシステムクリーチャーということで、言い過ぎかもしれませんが構築次第では新世代の死儀礼のシャーマンとなるかもしれません。
実際に回してみて気づいた点についていくつか挙げていきます。
3/4になるためにはこのデッキでは3ターン目以降になるので、基本的にはシステムクリーチャーとしての扱いで出していくことになります。火力があるデッキに関しては最初から3/4になるまでは構えるなどして展開は控えたいところですが、それでも1マナなのでテンポ損にはならないしソープロ耐性は元々ないので、1ターン目に死儀礼を展開していた時と同じように積極的に展開してもそこまで問題ないと感じました。
しかし3ターン目に3/4になるのはややハードルが高く、火力がある相手に対しては自身の能力で積極的に墓地を肥やしていく必要があります。テンポはやや悪くなりますがそこはシステムクリーチャー、構えるメリットも当然あります。不毛をサーチしてきたり、相手の不毛に対しては対象になっている土地をコストに能力を起動できるので耐性ができたり、不毛が効かない相手の場合はフェッチやキャノピーランドに交換しながら墓地を肥やしていくことができます。
そしてひとたび3/4になれば、稲妻圏外になるのはもちろんですがミラーマッチ際のマングースを一方的に討ち取れる他ネメシスにも討ち取られなくなるので、他にタルモのような地上生物を横並びした時でもお構いなしに殴りにいけるようになったのはマングースとの大きな違いと言えます。
メインではこのような使い方でマングースとの差別化を図っていますが、真価を発揮するのはやはりサイド後です。墓地対策にボジューカの沼、コンボ対策にカラカス、コントロール対策に幽霊街等、土地のシルバーバレット戦略を取れる万能さは、冒頭でも述べたようにさながら死儀礼と言っても過言ではないという感覚になります。
開墾者の採用により既存のカナスレで取っているカードで使い辛くなったものもあります。コントロール対策としてカナスレがサイドに採用している冬の宝珠は、マナを食う開墾者とは相性は良くありません。レンと六番との相性を考えるとそのまま採用しても悪くはないですが、開墾者が3/4になる前に出してしまうとなかなか墓地が肥えなくなるのでやや出すタイミングに制限がかかってしまうのがネック。森の知恵や硫黄の渦等の別のカードでの対策を検討する必要があります。
以上を踏まえ、現段階で調整したレシピはこちらです。
4秘密を掘り下げるもの
4エルフの開墾者
2タルモゴイフ
2真の名の宿敵
12
4渦まく知識
4思案
4稲妻
4もみ消し
2呪文貫き
2呪文嵌め
2レンと六番
4目くらまし
4意志の力
30
3Tropical Island
2Volcanic Island
1焦熱島嶼域
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
4不毛の大地
18
SB
1古の遺恨
2燃え殻蔦
1四肢切断
2外科的摘出
1紅蓮破
1水流破
1狼狽の嵐
1夏の帳
1森の知恵
1レンと六番
1ボジューカの沼
1カラカス
1幽霊街
15
サイドボードは、コントロール対策の冬の宝珠は開墾者との相性の関係上不採用とし、代わりに追加のレンと六番・森の知恵と、燃え殻蔦を2枚採用しています。前述の通り、シルバーバレット戦略を取るために1枚挿しの土地を複数採用。レンと六番の枚数も増やすことで使い回しやすくします。
また、M20から注目カードである夏の帳も採用しています。紅蓮破と狼狽の嵐の両方の役割を持たせられてアドまで取れるのが強いので、使い勝手が良ければ増量も考え中。
現在のメタは4Cデルバーやカナスレが台頭してきているので、水没の強さも相対的に戻ってきています。今回は枠の関係上不採用にしていますが、今後は何か削ってでも入れる可能性は十分にあります。
まず結論から言えば、想定通りレガシーでも十分に使えるカードパワーを持っていると感じました。クロックを刻めるシステムクリーチャーということで、言い過ぎかもしれませんが構築次第では新世代の死儀礼のシャーマンとなるかもしれません。
実際に回してみて気づいた点についていくつか挙げていきます。
3/4になるためにはこのデッキでは3ターン目以降になるので、基本的にはシステムクリーチャーとしての扱いで出していくことになります。火力があるデッキに関しては最初から3/4になるまでは構えるなどして展開は控えたいところですが、それでも1マナなのでテンポ損にはならないしソープロ耐性は元々ないので、1ターン目に死儀礼を展開していた時と同じように積極的に展開してもそこまで問題ないと感じました。
しかし3ターン目に3/4になるのはややハードルが高く、火力がある相手に対しては自身の能力で積極的に墓地を肥やしていく必要があります。テンポはやや悪くなりますがそこはシステムクリーチャー、構えるメリットも当然あります。不毛をサーチしてきたり、相手の不毛に対しては対象になっている土地をコストに能力を起動できるので耐性ができたり、不毛が効かない相手の場合はフェッチやキャノピーランドに交換しながら墓地を肥やしていくことができます。
そしてひとたび3/4になれば、稲妻圏外になるのはもちろんですがミラーマッチ際のマングースを一方的に討ち取れる他ネメシスにも討ち取られなくなるので、他にタルモのような地上生物を横並びした時でもお構いなしに殴りにいけるようになったのはマングースとの大きな違いと言えます。
メインではこのような使い方でマングースとの差別化を図っていますが、真価を発揮するのはやはりサイド後です。墓地対策にボジューカの沼、コンボ対策にカラカス、コントロール対策に幽霊街等、土地のシルバーバレット戦略を取れる万能さは、冒頭でも述べたようにさながら死儀礼と言っても過言ではないという感覚になります。
開墾者の採用により既存のカナスレで取っているカードで使い辛くなったものもあります。コントロール対策としてカナスレがサイドに採用している冬の宝珠は、マナを食う開墾者とは相性は良くありません。レンと六番との相性を考えるとそのまま採用しても悪くはないですが、開墾者が3/4になる前に出してしまうとなかなか墓地が肥えなくなるのでやや出すタイミングに制限がかかってしまうのがネック。森の知恵や硫黄の渦等の別のカードでの対策を検討する必要があります。
以上を踏まえ、現段階で調整したレシピはこちらです。
4秘密を掘り下げるもの
4エルフの開墾者
2タルモゴイフ
2真の名の宿敵
12
4渦まく知識
4思案
4稲妻
4もみ消し
2呪文貫き
2呪文嵌め
2レンと六番
4目くらまし
4意志の力
30
3Tropical Island
2Volcanic Island
1焦熱島嶼域
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
4不毛の大地
18
SB
1古の遺恨
2燃え殻蔦
1四肢切断
2外科的摘出
1紅蓮破
1水流破
1狼狽の嵐
1夏の帳
1森の知恵
1レンと六番
1ボジューカの沼
1カラカス
1幽霊街
15
サイドボードは、コントロール対策の冬の宝珠は開墾者との相性の関係上不採用とし、代わりに追加のレンと六番・森の知恵と、燃え殻蔦を2枚採用しています。前述の通り、シルバーバレット戦略を取るために1枚挿しの土地を複数採用。レンと六番の枚数も増やすことで使い回しやすくします。
また、M20から注目カードである夏の帳も採用しています。紅蓮破と狼狽の嵐の両方の役割を持たせられてアドまで取れるのが強いので、使い勝手が良ければ増量も考え中。
現在のメタは4Cデルバーやカナスレが台頭してきているので、水没の強さも相対的に戻ってきています。今回は枠の関係上不採用にしていますが、今後は何か削ってでも入れる可能性は十分にあります。
前回の続きです。
5、夏の帳
秋の帳の強化版。プレイヤー自身も呪禁を得られるようになったのとドローが付いて2対1交換できるようになったのが非常に大きい。除去やバウンスを弾いたり打ち消し呪文の対抗手段として使うのはもちろんだが、ハンデスに対しても撃てるので気軽に2対1が取れるようになった。尚且つ相手がANTだった場合はそのターン苦悶の触手による即死からも守れるので、ほぼ確実に延命できるようになる。
レガシーでは青と黒が強いのも相まって効く相手が多く、感染デッキのような除去とハンデスに弱いデッキや紅蓮破を入れられない緑を含むあらゆるデッキが代わりのサイド候補として重宝しそう。
6、多用途の鍵
通電式キーと比べると自身をアンタップできなくなったが、マナバーンのない今やコスト調整をする必要もなくなったので、単純にアンブロック効果が追加された上位互換と見て良い。ポスト系やMUDで序盤はマナ加速に貢献しつつ展開したフィニッシャーがブロックさせられないようにして、キルターンを早めるのに役立つだろう。
7、睡蓮の原野
睡蓮の谷間の調整版。呪禁を得たことで元祖の最大の弱点を克服し、アンタップ状態の土地を生け贄に捧げなくてもよくなったが、自身がタップインなのでテンポが悪くなった。このままではただ呪禁を持ったテンポの悪い土地なので何の役にも立たないが、それでも使ってみたいという動機がいくつかある。
1つ目は血染めの太陽との併用。先に血染めの太陽を設置できれば睡蓮の原野のデメリット部分が全て解消されるので本来より一気に2マナ分ジャンプできるのが強烈。2ターン目から5マナ域に到達することも可能なので、赤単スニークなら即コンボを始動できる。
そして2つ目の使い道として考えているのが、白ストンピィで大変動と一緒に使うという方法。テンポを犠牲にしてでも敢えて3つの土地を1つにまとめることで、大変動の土地の生け贄効果を自分だけ実質帳消しにすることができる。元々裏切り者の都やトロウケアの敷石は大変動と相性が良いが、それらの土地は睡蓮の原野の生け贄にする土地としてもうってつけなので無駄がない。ちなみに大変動はPWに関しては1体も残すことなく問答無用で一掃できるので、PWの多い現環境が地味に追い風になっているのもポイント。
5、夏の帳
秋の帳の強化版。プレイヤー自身も呪禁を得られるようになったのとドローが付いて2対1交換できるようになったのが非常に大きい。除去やバウンスを弾いたり打ち消し呪文の対抗手段として使うのはもちろんだが、ハンデスに対しても撃てるので気軽に2対1が取れるようになった。尚且つ相手がANTだった場合はそのターン苦悶の触手による即死からも守れるので、ほぼ確実に延命できるようになる。
レガシーでは青と黒が強いのも相まって効く相手が多く、感染デッキのような除去とハンデスに弱いデッキや紅蓮破を入れられない緑を含むあらゆるデッキが代わりのサイド候補として重宝しそう。
6、多用途の鍵
通電式キーと比べると自身をアンタップできなくなったが、マナバーンのない今やコスト調整をする必要もなくなったので、単純にアンブロック効果が追加された上位互換と見て良い。ポスト系やMUDで序盤はマナ加速に貢献しつつ展開したフィニッシャーがブロックさせられないようにして、キルターンを早めるのに役立つだろう。
7、睡蓮の原野
睡蓮の谷間の調整版。呪禁を得たことで元祖の最大の弱点を克服し、アンタップ状態の土地を生け贄に捧げなくてもよくなったが、自身がタップインなのでテンポが悪くなった。このままではただ呪禁を持ったテンポの悪い土地なので何の役にも立たないが、それでも使ってみたいという動機がいくつかある。
1つ目は血染めの太陽との併用。先に血染めの太陽を設置できれば睡蓮の原野のデメリット部分が全て解消されるので本来より一気に2マナ分ジャンプできるのが強烈。2ターン目から5マナ域に到達することも可能なので、赤単スニークなら即コンボを始動できる。
そして2つ目の使い道として考えているのが、白ストンピィで大変動と一緒に使うという方法。テンポを犠牲にしてでも敢えて3つの土地を1つにまとめることで、大変動の土地の生け贄効果を自分だけ実質帳消しにすることができる。元々裏切り者の都やトロウケアの敷石は大変動と相性が良いが、それらの土地は睡蓮の原野の生け贄にする土地としてもうってつけなので無駄がない。ちなみに大変動はPWに関しては1体も残すことなく問答無用で一掃できるので、PWの多い現環境が地味に追い風になっているのもポイント。
灯争大戦・モダンホライゾンと、レガシーに影響を与えたセットが立て続けに発売されメタが目まぐるしく変化しており若干食傷気味ですが、そんな中早くもM20のフルスポイラーが公開となりました。
MOでは紙の発売よりも早く使えるので、それまでに注目カードを挙げなければいけなくて若干慌ててしまいますが、基本セットにあるまじき(?)面白そうなカードがいくつかあるので、早速今回も挙げていきたいと思います。
1、霊気の疾風
ライブラリートップかボトムの選択権は相手なのでほとんどの場合トップになると思われるが、対象が対抗色限定になった分呪文のみならずパーマネントにも対処できるようになった記憶の欠落のような使い勝手。
普通に使っても1ターン遅らせるだけだが確実に1対1交換できてテンポも取れれば悪くはないし、水没のようにフェッチなどのシャッフル手段に対応して緑の硬い生物や流行りのレンと六番のようなパーマネントに撃てば範囲の広い実質除去として扱える。更に突然の衰微のような打ち消せない呪文にも効くのが大きく、青いデッキのサイドに取って相手の計算を狂わせたい。
2、軍団の最期
黒待望の軽い追放除去。ソーサリーでコストも2マナなのでテンポは取れないし範囲も狭いが、2マナ以下の強力な生物がひしめくレガシーでは対象に困ることはまずない。しかも撲滅と違いライブラリーの代わりに戦場に干渉できるようになったおかげでアドを取りやすくなった。墓所這いや恐血鬼のような墓地から復活する生物に効果を発揮するのはもちろん、同名トークンを一掃できたり2マナでマリットレイジにも対処できることまでできると思えば十分破格の性能と言える。
普段はあまり除去を向けたくない、瞬唱のような戦場に出た時点で仕事をするような生物やダブれば腐るサリアのような生物にも効果的。次を出される前にこれによりハンドから抜ける可能性を考慮すれば積極的に当てにいけるのでより腐りにくく、しかも黒にはハンデスがあるので前方確認からアドを狙いやすい。
副作用的な効果であるピーピングの効果も決して馬鹿にならない。2発目のこれを活かせやすくなるので相手の行動を制限させられるし、セラピーとの相性も抜群。このように黒ならハンデスと併用していることがほとんどなので、下手に狙い撃とうとせずに除去を当てられるタイミングが来れば積極的に当てていく使い方をするのが吉。
3、傲慢な血王、ソリン
3マナながらシングルシンボルなので黒ストンピィで使いやすいPWは非常にありがたい。ストンピィ系で使えそうな吸血鬼は有力な候補は少ないが、それでも吸血鬼ストンピィを組むひとつの動機になる。
当然-3の能力がメインだが、下手に大型の吸血鬼の踏み倒しを狙わなくても、血統の守り手やゲトの裏切り者、カリタス辺りのダブシン4マナ域を1ターン目から出せるようになるだけでも十分。それで序盤はソリンを守ることができるので、+1で強化しながらもう一度踏み倒すことができればマナ加速として十分に役割を果たせたと言えるのではないか。特に血統の守り手がうまく回れば、トークンを生け贄に2番目の+1も活かすことができる。
ただ吸血鬼ならなんでも踏み倒せるので、せっかくならそれもある程度狙うことを考えると、やはりドロスの大長との併用が真っ先に思い浮かぶ。ゲーム開始時にドレインしてライフレースを有利にしつつ、金属モックスで刻印してよし、ソリンを引けば踏み倒してよしなので黒ストンピィでは使いやすくなる。しかし引きムラに左右されやすいストンピィ系ではあまりコンボに寄せ過ぎないようにした方が良さそうか。
4、エルフの開墾者
土地をサーチしながら自身の能力で土地を墓地に肥やして成長するという、1マナ生物ながら聖遺の騎士の能力と酷似している自己完結した能力を持っている。
個人的にM20で最も注目しているカードで、あらゆるデッキに入る可能性を感じる生物。マナコストやスペックから聖遺の騎士よりも高速なデッキ向けなことから、以下のようなデッキに入るのではないかと考える。
まず1つ目の選択肢はRUGデルバーの新しい1マナ域クロック兼不毛サーチ要員として。除去耐性は流石にマングースに敵わないが、序盤から3/4になれるので火力耐性は持っており戦闘にも強くなっているのでクロックとして見劣りしない性能。そして肝心の能力で不毛をサーチして、もみ消しと更には新戦力のレンと六番という相方を利用して徹底したマナ否定戦略を取りたい。
2つ目はBG系デプスにおけるコンボの潤滑油として。これ1枚で序盤からコンボを完成させることができる。もちろん除去は当たってしまうが、同じ潤滑油の役割を持つボブと併用することで、マスト除去の水増しと考えることもできる。仮にコンボが妨害されたとしてもビートして勝つという選択肢も取れるので、タルモのような戦闘に強い生物も併用すればコンボに頼り過ぎない丸い構成にすることも可能。
3つ目はエルフデッキのガイアの揺籃の地サーチ要員として。単体で強い能力を持っているのにこれ自身がエルフで部族の恩恵を受けるというのがまず胡散臭い。そしてサーチで高確率でクレイドルにアクセスできるようになれば、緑頂点からのビヒモスルートもお手のもの。ただしエルフはある程度デッキの枠が固まっているので、枠を作れるかが問題。
MOでは紙の発売よりも早く使えるので、それまでに注目カードを挙げなければいけなくて若干慌ててしまいますが、基本セットにあるまじき(?)面白そうなカードがいくつかあるので、早速今回も挙げていきたいと思います。
1、霊気の疾風
ライブラリートップかボトムの選択権は相手なのでほとんどの場合トップになると思われるが、対象が対抗色限定になった分呪文のみならずパーマネントにも対処できるようになった記憶の欠落のような使い勝手。
普通に使っても1ターン遅らせるだけだが確実に1対1交換できてテンポも取れれば悪くはないし、水没のようにフェッチなどのシャッフル手段に対応して緑の硬い生物や流行りのレンと六番のようなパーマネントに撃てば範囲の広い実質除去として扱える。更に突然の衰微のような打ち消せない呪文にも効くのが大きく、青いデッキのサイドに取って相手の計算を狂わせたい。
2、軍団の最期
黒待望の軽い追放除去。ソーサリーでコストも2マナなのでテンポは取れないし範囲も狭いが、2マナ以下の強力な生物がひしめくレガシーでは対象に困ることはまずない。しかも撲滅と違いライブラリーの代わりに戦場に干渉できるようになったおかげでアドを取りやすくなった。墓所這いや恐血鬼のような墓地から復活する生物に効果を発揮するのはもちろん、同名トークンを一掃できたり2マナでマリットレイジにも対処できることまでできると思えば十分破格の性能と言える。
普段はあまり除去を向けたくない、瞬唱のような戦場に出た時点で仕事をするような生物やダブれば腐るサリアのような生物にも効果的。次を出される前にこれによりハンドから抜ける可能性を考慮すれば積極的に当てにいけるのでより腐りにくく、しかも黒にはハンデスがあるので前方確認からアドを狙いやすい。
副作用的な効果であるピーピングの効果も決して馬鹿にならない。2発目のこれを活かせやすくなるので相手の行動を制限させられるし、セラピーとの相性も抜群。このように黒ならハンデスと併用していることがほとんどなので、下手に狙い撃とうとせずに除去を当てられるタイミングが来れば積極的に当てていく使い方をするのが吉。
3、傲慢な血王、ソリン
3マナながらシングルシンボルなので黒ストンピィで使いやすいPWは非常にありがたい。ストンピィ系で使えそうな吸血鬼は有力な候補は少ないが、それでも吸血鬼ストンピィを組むひとつの動機になる。
当然-3の能力がメインだが、下手に大型の吸血鬼の踏み倒しを狙わなくても、血統の守り手やゲトの裏切り者、カリタス辺りのダブシン4マナ域を1ターン目から出せるようになるだけでも十分。それで序盤はソリンを守ることができるので、+1で強化しながらもう一度踏み倒すことができればマナ加速として十分に役割を果たせたと言えるのではないか。特に血統の守り手がうまく回れば、トークンを生け贄に2番目の+1も活かすことができる。
ただ吸血鬼ならなんでも踏み倒せるので、せっかくならそれもある程度狙うことを考えると、やはりドロスの大長との併用が真っ先に思い浮かぶ。ゲーム開始時にドレインしてライフレースを有利にしつつ、金属モックスで刻印してよし、ソリンを引けば踏み倒してよしなので黒ストンピィでは使いやすくなる。しかし引きムラに左右されやすいストンピィ系ではあまりコンボに寄せ過ぎないようにした方が良さそうか。
4、エルフの開墾者
土地をサーチしながら自身の能力で土地を墓地に肥やして成長するという、1マナ生物ながら聖遺の騎士の能力と酷似している自己完結した能力を持っている。
個人的にM20で最も注目しているカードで、あらゆるデッキに入る可能性を感じる生物。マナコストやスペックから聖遺の騎士よりも高速なデッキ向けなことから、以下のようなデッキに入るのではないかと考える。
まず1つ目の選択肢はRUGデルバーの新しい1マナ域クロック兼不毛サーチ要員として。除去耐性は流石にマングースに敵わないが、序盤から3/4になれるので火力耐性は持っており戦闘にも強くなっているのでクロックとして見劣りしない性能。そして肝心の能力で不毛をサーチして、もみ消しと更には新戦力のレンと六番という相方を利用して徹底したマナ否定戦略を取りたい。
2つ目はBG系デプスにおけるコンボの潤滑油として。これ1枚で序盤からコンボを完成させることができる。もちろん除去は当たってしまうが、同じ潤滑油の役割を持つボブと併用することで、マスト除去の水増しと考えることもできる。仮にコンボが妨害されたとしてもビートして勝つという選択肢も取れるので、タルモのような戦闘に強い生物も併用すればコンボに頼り過ぎない丸い構成にすることも可能。
3つ目はエルフデッキのガイアの揺籃の地サーチ要員として。単体で強い能力を持っているのにこれ自身がエルフで部族の恩恵を受けるというのがまず胡散臭い。そしてサーチで高確率でクレイドルにアクセスできるようになれば、緑頂点からのビヒモスルートもお手のもの。ただしエルフはある程度デッキの枠が固まっているので、枠を作れるかが問題。
6/15第111回KMC結果
2019年6月17日 Magic: The Gathering今回は参加人数106人の7回戦。
デッキは以前の日記の通り、秘技術師を得て新たに調整した執着的探訪入りURデルバーです。若干調整を加えてレシピは下記の通りにまとまりました。
4秘密を掘り下げるもの
4僧院の速槍
4戦慄衆の秘儀術師
2真の名の宿敵
14
4渦まく知識
4思案
2定業
3執着的探訪
4稲妻
3稲妻の連鎖
1削剥
1発展の代価
4目くらまし
4意志の力
30
3Volcanic Island
2島
1山
4沸騰する小湖
4霧深い雨林
2乾燥大地
16
SB
1破壊放題
1削剥
1ゴブリンのクレーター掘り
1電弧の痕跡
1イゼットの静電術師
1発展の代価
2外科的摘出
2紅蓮破
2大歓楽の幻霊
1高山の月
1カラカス
15
1回戦目:ミラクル ○○
1Gはネメシス探訪で打ち消しを補充し採決をきっちり捌いて勝ち、2Gはソープロにサージカルして除去を減らし、速槍探訪ネメシスで勝ち。
2回戦目:アルーレン ××
氷牙のコアトルと悪意の大梟の8枚体制で序盤を守られ、コンボで負け。2Gはライフレース相手残り4こちら返しで死ぬライフの場面、ネメシスが立っていて火力を探したら探訪トップできたので喜び勇んで殴ったが、衰微で探訪を破られあえなく撃沈。
対戦相手がコアトルの能力を勘違いしていたのか、氷雪パーマネントが他に2つの時に逸脱者をブロックしてくれたのはラッキーだった。しかし2タテ。
3回戦目:グリクシス忍者 ○×○
1Gはあまり展開されなくて忍者も出てこずグリコンと思いながら戦ったが普通に押して勝ち。2Gで大梟から堕ちた忍びが飛んできてようやく忍者と発覚。5点クロック+サボタージュ能力でズタボロにされ負け。3Gは有利なダメージレースになりながらネメシスが通って相手は間に合わず押し切り。
4回戦目:BGデプス ○○
1Gはこちら土地なしダブマリvs相手トリマリ。序盤グダグダになりながらも2ターン後に土地を引き込み、相手はハンデスしかなくデルバーで勝ち。2Gは序盤針で演劇の舞台を刺してボブ呪詛術師を除去しデルバー探訪でさらなる打ち消しと除去を補充し勝ち。
相手の事故もあったとは思うが、苦手なだけにこのマッチを2タテできたのは嬉しい。
5回戦目:グリセルストーム ×○×
1Gは早々に暴露でハンド確認されコンボ決められ負け。2Gは1T目にサイドカラカスをセットし相手悶絶。更に大歓楽探訪でゴリゴリ削りつつ火力打ち消しパンパン。苦し紛れにこちらの秘技術師を釣るが除去したら相手投了。3Gはあまり強くないハンドだったが思案と紅蓮破があったのでキープ。ハンデスで思案ではなく紅蓮破を落とされる。相手も土地1枚で詰まっていただので紅蓮破の方を落としてきたのだと思い、ブレストを引き込んだデイズで止めて詰まらせにいく。秘技術師を着地させたが返しにラスアナを出され+1で動きを封じられてしまう。その後奥義まで辿り着かれるまで土地以外引けず全く何もできずに負け。正直悔しすぎる負け方。
6回戦目:ミラクル ××
1回戦目とは打って変わってこれでもかと綺麗に裁かれ、ナーセットジェイスでアド負け。頼みの綱のネメシスは一切引けず。ナーセットを2、3枚取っているタイプで、執着的探訪が仇となってしまった。
7回戦目:MUD ○○
チャリスが飛んで来ず墳墓で自傷しまくり。秘技術師が除去られず金属細工師はきっちり除去して発展の代価で〆。
というわけで、4-3の辛うじて勝ち越し。
コアトルや新忍者など、早速新しいカードが使われていたので非常に面白い一日となりました。
ミラクル相手には秘技術師よりも嵐追いの方が強いので、次回は枚数を散らすことも検討中。執着的探訪に関してはギタ調が禁止になっても使い心地は上々ったので、果敢型URデルバーでは引き続き使っていきたいと思います。
デッキは以前の日記の通り、秘技術師を得て新たに調整した執着的探訪入りURデルバーです。若干調整を加えてレシピは下記の通りにまとまりました。
4秘密を掘り下げるもの
4僧院の速槍
4戦慄衆の秘儀術師
2真の名の宿敵
14
4渦まく知識
4思案
2定業
3執着的探訪
4稲妻
3稲妻の連鎖
1削剥
1発展の代価
4目くらまし
4意志の力
30
3Volcanic Island
2島
1山
4沸騰する小湖
4霧深い雨林
2乾燥大地
16
SB
1破壊放題
1削剥
1ゴブリンのクレーター掘り
1電弧の痕跡
1イゼットの静電術師
1発展の代価
2外科的摘出
2紅蓮破
2大歓楽の幻霊
1高山の月
1カラカス
15
1回戦目:ミラクル ○○
1Gはネメシス探訪で打ち消しを補充し採決をきっちり捌いて勝ち、2Gはソープロにサージカルして除去を減らし、速槍探訪ネメシスで勝ち。
2回戦目:アルーレン ××
氷牙のコアトルと悪意の大梟の8枚体制で序盤を守られ、コンボで負け。2Gはライフレース相手残り4こちら返しで死ぬライフの場面、ネメシスが立っていて火力を探したら探訪トップできたので喜び勇んで殴ったが、衰微で探訪を破られあえなく撃沈。
対戦相手がコアトルの能力を勘違いしていたのか、氷雪パーマネントが他に2つの時に逸脱者をブロックしてくれたのはラッキーだった。しかし2タテ。
3回戦目:グリクシス忍者 ○×○
1Gはあまり展開されなくて忍者も出てこずグリコンと思いながら戦ったが普通に押して勝ち。2Gで大梟から堕ちた忍びが飛んできてようやく忍者と発覚。5点クロック+サボタージュ能力でズタボロにされ負け。3Gは有利なダメージレースになりながらネメシスが通って相手は間に合わず押し切り。
4回戦目:BGデプス ○○
1Gはこちら土地なしダブマリvs相手トリマリ。序盤グダグダになりながらも2ターン後に土地を引き込み、相手はハンデスしかなくデルバーで勝ち。2Gは序盤針で演劇の舞台を刺してボブ呪詛術師を除去しデルバー探訪でさらなる打ち消しと除去を補充し勝ち。
相手の事故もあったとは思うが、苦手なだけにこのマッチを2タテできたのは嬉しい。
5回戦目:グリセルストーム ×○×
1Gは早々に暴露でハンド確認されコンボ決められ負け。2Gは1T目にサイドカラカスをセットし相手悶絶。更に大歓楽探訪でゴリゴリ削りつつ火力打ち消しパンパン。苦し紛れにこちらの秘技術師を釣るが除去したら相手投了。3Gはあまり強くないハンドだったが思案と紅蓮破があったのでキープ。ハンデスで思案ではなく紅蓮破を落とされる。相手も土地1枚で詰まっていただので紅蓮破の方を落としてきたのだと思い、ブレストを引き込んだデイズで止めて詰まらせにいく。秘技術師を着地させたが返しにラスアナを出され+1で動きを封じられてしまう。その後奥義まで辿り着かれるまで土地以外引けず全く何もできずに負け。正直悔しすぎる負け方。
6回戦目:ミラクル ××
1回戦目とは打って変わってこれでもかと綺麗に裁かれ、ナーセットジェイスでアド負け。頼みの綱のネメシスは一切引けず。ナーセットを2、3枚取っているタイプで、執着的探訪が仇となってしまった。
7回戦目:MUD ○○
チャリスが飛んで来ず墳墓で自傷しまくり。秘技術師が除去られず金属細工師はきっちり除去して発展の代価で〆。
というわけで、4-3の辛うじて勝ち越し。
コアトルや新忍者など、早速新しいカードが使われていたので非常に面白い一日となりました。
ミラクル相手には秘技術師よりも嵐追いの方が強いので、次回は枚数を散らすことも検討中。執着的探訪に関してはギタ調が禁止になっても使い心地は上々ったので、果敢型URデルバーでは引き続き使っていきたいと思います。
もう発売日まで来てしまいましたが、これで最後になります。
22、ケイヤの手管
コラコマと似たような4モードから2つ選択できる便利なインスタント。基本は布告とトークン生成が目当てではあるが、それ以外の能力は後ろ向きでコラコマほど汎用性は高くない。
しかしライフゲインもエスパーのようなコントロール寄りのデッキなら少しでもゲームを長引かせられるし、トークンはインスタントで出る装備先として最適。墓地対策モードもリアニのような高速で墓地を使う相手には効果は薄いものの、ドレッジや探査生物等の墓地利用の抑制や、瞬唱や流行りの秘儀術師の能力を空振りさせる使い道もあるので以外と腐らない。双呪を持っているので後半に引いても強いのはコラコマにはない強み。
23、不確定な船乗り
青白の新たなヘイトベアー。誘発条件はレオヴォルドと同じで、ドローの代わりにマナを要求し支払えなければ打ち消すようになっている。
対ANTのハンデスや苦悶の触手対策になるのはもちろん、生物の除去耐性を遅らせたり不毛やリシャポを重くすることでテンポを取りに行けるので、サイドはもちろんデッキによってはメインから入れるのもアリ。しかも能力が重複するタイプのヘイトベアー且つ対戦相手だけに効くので、複数枚入れても腐らないのも魅力。
多相を持っていることで、人間やスピリット、スリヴァーなどの部族デッキで使いやすく、ヘイトベアーが不足している部族デッキでは気軽に補っていける。
24、レンと六番
名前のダサさはさておき、多色なものの2マナのPWで初期忠誠度が3あり、+1でアドを取ることができて稲妻圏外になる時点で強い。小マイナス能力はティムでこちらもアドに繋がる能力なのに-1なので連打が利くという、2マナPWとは思えない性能。大マイナスは直接アドバンテージには繋がらないものの、後半の腐った土地を呪文に変えれば間接的にアドは取れることになるし、+1と相性がいいので決して弱くない。
カナスレのサイドに取って不毛ハメ兼相手の不毛ハメ防止として入れたり、土地単やアグロロームのようなデッキで汎用性が高くなったロームとして使うのが良さそう。
25、屑鉄場の再構成機
MUDやスティールストンピィ待望の一枚。
タップが必要だがマナいらずで使えるサクり台能力がとにかく強力で、例えばスティールストンピィでは搭載歩行機械をサクってトークンをばら撒きつつ構築物である歩行バリスタを引っ張ってこれるのが強力。MUDでもカルドーサの鍛冶場主を単体でサーチできるのでより安定した動きが取れるようになった。
自身も構築物のため、ターンが帰って来れば除去に対して最悪自らをサクって延々とコレを持ってくることもできるし、接合のおかげで搭載歩行機械や歩行バリスタが横にいればシナジーまでするので非常に粘り強く戦うことができそう。
26、ヘリオッドの高潔の聖堂
エンチャント版アカデミーの廃墟。エンチャントレスに入れることで打ち消された女魔術師の存在を拾うことができるようになり、ドローできなくて止まって何もできず負けるという事態になりにくくなった。
他には青白の相殺を使ったコントロールで、墓地に落ちたエネルギーフィールドを回収しつつマナコスト2の呪文を相殺で打ち消す、という使い方も面白そう。
27、虹色の眺望
青白(t赤)奇跡や青白石鍛冶にとっての待望の1枚。基本地形ばかり並べたいのでデュアランを持ってこれるフェッチにあまり拘りがなく、島と平地をサーチできるフェッチが単純に8枚になったので、序盤のマナ基盤安定化にかなり貢献しそう。t赤奇跡も、基本に帰れを自分で使っていたり不毛に弱いという関係上ボルカはあまり持ってきたくないので、島も平地も山も持ってこれるコレは使い勝手が良い。
反面、基本地形を取っていてもデュアランを積極的に持ってくるURデルバーやグリコンのようなデッキには不向き。前者は1ターン目に赤い生物を出しつつ目くらましを構えるにはボルカからサーチしないといけないし、グリコンは序盤ドロー操作しながらできるだけ早くヒムを撃たないといけないので基本地形からゆっくりサーチしているヒマはあまりないので使い辛い。
22、ケイヤの手管
コラコマと似たような4モードから2つ選択できる便利なインスタント。基本は布告とトークン生成が目当てではあるが、それ以外の能力は後ろ向きでコラコマほど汎用性は高くない。
しかしライフゲインもエスパーのようなコントロール寄りのデッキなら少しでもゲームを長引かせられるし、トークンはインスタントで出る装備先として最適。墓地対策モードもリアニのような高速で墓地を使う相手には効果は薄いものの、ドレッジや探査生物等の墓地利用の抑制や、瞬唱や流行りの秘儀術師の能力を空振りさせる使い道もあるので以外と腐らない。双呪を持っているので後半に引いても強いのはコラコマにはない強み。
23、不確定な船乗り
青白の新たなヘイトベアー。誘発条件はレオヴォルドと同じで、ドローの代わりにマナを要求し支払えなければ打ち消すようになっている。
対ANTのハンデスや苦悶の触手対策になるのはもちろん、生物の除去耐性を遅らせたり不毛やリシャポを重くすることでテンポを取りに行けるので、サイドはもちろんデッキによってはメインから入れるのもアリ。しかも能力が重複するタイプのヘイトベアー且つ対戦相手だけに効くので、複数枚入れても腐らないのも魅力。
多相を持っていることで、人間やスピリット、スリヴァーなどの部族デッキで使いやすく、ヘイトベアーが不足している部族デッキでは気軽に補っていける。
24、レンと六番
名前のダサさはさておき、多色なものの2マナのPWで初期忠誠度が3あり、+1でアドを取ることができて稲妻圏外になる時点で強い。小マイナス能力はティムでこちらもアドに繋がる能力なのに-1なので連打が利くという、2マナPWとは思えない性能。大マイナスは直接アドバンテージには繋がらないものの、後半の腐った土地を呪文に変えれば間接的にアドは取れることになるし、+1と相性がいいので決して弱くない。
カナスレのサイドに取って不毛ハメ兼相手の不毛ハメ防止として入れたり、土地単やアグロロームのようなデッキで汎用性が高くなったロームとして使うのが良さそう。
25、屑鉄場の再構成機
MUDやスティールストンピィ待望の一枚。
タップが必要だがマナいらずで使えるサクり台能力がとにかく強力で、例えばスティールストンピィでは搭載歩行機械をサクってトークンをばら撒きつつ構築物である歩行バリスタを引っ張ってこれるのが強力。MUDでもカルドーサの鍛冶場主を単体でサーチできるのでより安定した動きが取れるようになった。
自身も構築物のため、ターンが帰って来れば除去に対して最悪自らをサクって延々とコレを持ってくることもできるし、接合のおかげで搭載歩行機械や歩行バリスタが横にいればシナジーまでするので非常に粘り強く戦うことができそう。
26、ヘリオッドの高潔の聖堂
エンチャント版アカデミーの廃墟。エンチャントレスに入れることで打ち消された女魔術師の存在を拾うことができるようになり、ドローできなくて止まって何もできず負けるという事態になりにくくなった。
他には青白の相殺を使ったコントロールで、墓地に落ちたエネルギーフィールドを回収しつつマナコスト2の呪文を相殺で打ち消す、という使い方も面白そう。
27、虹色の眺望
青白(t赤)奇跡や青白石鍛冶にとっての待望の1枚。基本地形ばかり並べたいのでデュアランを持ってこれるフェッチにあまり拘りがなく、島と平地をサーチできるフェッチが単純に8枚になったので、序盤のマナ基盤安定化にかなり貢献しそう。t赤奇跡も、基本に帰れを自分で使っていたり不毛に弱いという関係上ボルカはあまり持ってきたくないので、島も平地も山も持ってこれるコレは使い勝手が良い。
反面、基本地形を取っていてもデュアランを積極的に持ってくるURデルバーやグリコンのようなデッキには不向き。前者は1ターン目に赤い生物を出しつつ目くらましを構えるにはボルカからサーチしないといけないし、グリコンは序盤ドロー操作しながらできるだけ早くヒムを撃たないといけないので基本地形からゆっくりサーチしているヒマはあまりないので使い辛い。
15、アイユーラの影響
色は違うがどちらも土地単で採用できる色且つ似ている部分が多い突撃の地鳴りとの比較になる。トークンなので除去としては使えないもののブロッカーとして守ることはできるし、攻める際はクロックが残るこちらの方が早くてアドバンテージも失っていないという所がポイント。決して引けを取らない性能と言えるのではないか。
あとは緑トリシンをいかに捻出するかが課題ではあるが、土地単では森を取っている分突撃の地鳴りに比べてだいぶ出しやすくなっているため、採用候補になりやすい。
16、溜め込み屋のアウフ
無のロッド内蔵のヘイトベアー。除去には引っかかりやすいものの緑頂点からサーチできる分サイドの枠を節約できるのは大きい。
マーベリックで使う際は自分の石鍛冶からサーチした装備品まで止まってしまうので要注意。
17、衝撃の足音
待機経由で唱えると速攻を持たないトークンが出るのはかなり遅いので踏み倒しが前提になるが、続唱などで4/4トランプル2体出るのは流石に強い。他にも雷電支配や墓地に落ちたら秘儀術師、約束の終焉で踏み倒せるので、こちらも併用してできるだけ待機を経由しないで唱えられる構築にすればレガシーでも十分通用しそう。
18、活性の力
これのおかげで、ぶっぱ月やチャリスを通してしまっても後引きで対処できるので簡単に詰まされる心配がなくなった。しかも対象を最大2つ取れるためうまくいけば2:2交換まで取れてしまうという、赤ストンピィにとっては悪夢のような1枚になりそう。
他にも対石鍛冶系の装備品+基本に帰れだったり、チャリス系デッキでは置物を2枚以上出す場面が多いので、ピッチスペルなのにテンポはおろかアドすらも失わない可能性も秘めているのは優秀。
19、蘇る死滅都市、ホガーク
MOではモダンで既に大暴れしている生物。縫い師への供給者などを利用してうまく墓地に落ちれば、最速2ターン目に8/8トランプルを出すことができる。
レガシーでも、墓地から唱えられることを利用してゾンバードメントに入れて、線の細い生物を補うために通常の探査生物の代わりとして使ってみたい。
20、氷牙のコアトル
条件付きながらも瞬速の付いた青緑版の悪意の大梟といったところ。
氷雪パーマネントを他に3つ用意する必要があるためブロッカーとしての即効性はないが、フェッチから氷雪土地をサーチできるのでそこまで条件は厳しくないし、黒を入れられないデッキで大梟のようなカードを取れるのはありがたい。
21、巧妙な潜入者
深き刻の忍者の追加枠。いやむしろ忍者デッキは青黒+αで組むのが基本と考えたら深き刻の忍者より強いこちらとまるまる入れ替えになりそう。忍者デッキではこのような軽くて使いやすい忍術を持つ生物が増えるのはありがたいので、百合子といいかなり層が厚くなってきて嬉しい限り。
色は違うがどちらも土地単で採用できる色且つ似ている部分が多い突撃の地鳴りとの比較になる。トークンなので除去としては使えないもののブロッカーとして守ることはできるし、攻める際はクロックが残るこちらの方が早くてアドバンテージも失っていないという所がポイント。決して引けを取らない性能と言えるのではないか。
あとは緑トリシンをいかに捻出するかが課題ではあるが、土地単では森を取っている分突撃の地鳴りに比べてだいぶ出しやすくなっているため、採用候補になりやすい。
16、溜め込み屋のアウフ
無のロッド内蔵のヘイトベアー。除去には引っかかりやすいものの緑頂点からサーチできる分サイドの枠を節約できるのは大きい。
マーベリックで使う際は自分の石鍛冶からサーチした装備品まで止まってしまうので要注意。
17、衝撃の足音
待機経由で唱えると速攻を持たないトークンが出るのはかなり遅いので踏み倒しが前提になるが、続唱などで4/4トランプル2体出るのは流石に強い。他にも雷電支配や墓地に落ちたら秘儀術師、約束の終焉で踏み倒せるので、こちらも併用してできるだけ待機を経由しないで唱えられる構築にすればレガシーでも十分通用しそう。
18、活性の力
これのおかげで、ぶっぱ月やチャリスを通してしまっても後引きで対処できるので簡単に詰まされる心配がなくなった。しかも対象を最大2つ取れるためうまくいけば2:2交換まで取れてしまうという、赤ストンピィにとっては悪夢のような1枚になりそう。
他にも対石鍛冶系の装備品+基本に帰れだったり、チャリス系デッキでは置物を2枚以上出す場面が多いので、ピッチスペルなのにテンポはおろかアドすらも失わない可能性も秘めているのは優秀。
19、蘇る死滅都市、ホガーク
MOではモダンで既に大暴れしている生物。縫い師への供給者などを利用してうまく墓地に落ちれば、最速2ターン目に8/8トランプルを出すことができる。
レガシーでも、墓地から唱えられることを利用してゾンバードメントに入れて、線の細い生物を補うために通常の探査生物の代わりとして使ってみたい。
20、氷牙のコアトル
条件付きながらも瞬速の付いた青緑版の悪意の大梟といったところ。
氷雪パーマネントを他に3つ用意する必要があるためブロッカーとしての即効性はないが、フェッチから氷雪土地をサーチできるのでそこまで条件は厳しくないし、黒を入れられないデッキで大梟のようなカードを取れるのはありがたい。
21、巧妙な潜入者
深き刻の忍者の追加枠。いやむしろ忍者デッキは青黒+αで組むのが基本と考えたら深き刻の忍者より強いこちらとまるまる入れ替えになりそう。忍者デッキではこのような軽くて使いやすい忍術を持つ生物が増えるのはありがたいので、百合子といいかなり層が厚くなってきて嬉しい限り。
前回に引き続き、注目カードを挙げていきます。
8、陰謀団の療法士
これはモダンホライゾンが発表した際に公開された時に書いた以前の日記の通り。
能力のタイミングに制限があるのが難点ではあるものの、ゾンバードメントではハンデス・サクり台・ディスカード手段の三役を1枚でこなせるので試してみたい。
9、終異種
変異種の亜種がついに黒で登場。
威迫・接死と+1/-1・-1/+1能力が非常に相性が良く、実質的にかなりブロックされにくい回避能力となっている上に、ブロックで討ち取られても2対1交換を強制できて不死によって復活できるし、4/4になって帰ってくるので+1/-1・-1/+1能力が更に活きるということもあり、個々の能力がそれぞれ非常に噛み合っているため戦闘においてはかなりの制圧力があると言える。
しかし除去耐性として見た場合の不死は、復活が1回きりであるということ、ソープロやバウンスには無力で元々火力耐性もあり破壊やマイナス修正除去以外にはあまり意味がないという側面もあるので、他の亜種と比べたら信頼性は薄いのが難点ではある。
これ自体4マナと重いので、黒ストンピィで高速召喚して苦手な除去はチャリスで補いたい。
10、疫病を仕組むもの
生物に仕組まれた疫病が内蔵され、更に対戦相手にしか影響しなくなっただけでもかなり優秀なのに、自身に接死まで付いているという大盤振る舞いはすごい。生物なので除去されやすいものの、タフ1をシャットアウトしつつクロックを刻み大型生物にも戦闘で対処できるので、使い勝手はかなり良さそう。
同じマナコストで似たような生物に疫病吐きがいるが、こちらも決して悪くはないものの自分の生物にもダメージが飛ぶためトークン戦略が取れず構築の幅が狭まってしまうが、疫病を仕組むものならなんら問題ない。
個人的には終異種と同様黒ストンピィでの採用が本命。苦手なネメシスやヤンパイに対応できてマルドゥの急襲指揮者との併用も可能になったので、かなり強化されるのではないか。
11、スランの医師、ヨーグモス
またしても黒ストンピィ要員の候補。
サクり台能力がマナいらずで戦場に直接触れてアドまで取れる能力なので、前述のような黒ストンピィでトークン戦略を取れるような構築をすればかなりの盤面制圧力を持つことができる。終異種と併用すれば、不死によって乗った+1/+1カウンターと-1/-1カウンターを相殺させ何度でも不死を利用する、ということも可能。
増殖の能力は単体では1/-1カウンターを増殖する以外使い道はないが、PWと併用するなどして自然に活かせられる構築をして利用したい。
12、ゴブリンの技師
起動型能力はゴブリンの溶接工とはマナがかかったり交換ではなく生贄がコストだったりと細かな違いはあるが、ペインターにおけるチャリスに引っかからないサーチできる溶接工としての採用が真っ先に考えられる。
またはグリクシステゼレットのソプターコンボのサーチとして、弱者の剣を直接墓地にサーチできるのが強いし、鋳造所も生きてターンが返れば自身でリアニメイトできるので足りない方を補うコンボの潤滑油として使えそう。
13、パシャリク・モンス
ゴブリンストンピィに入れたい1枚。12ラブルでトークンを大量生産して、戦闘でトークンが死んでも1点飛ばせるようになることでタフ2以上も対処できるように。
トークン生成能力も上記の能力と噛み合っており、更に自身もサクれるので伝説も気にならない。
14、悪ふざけ
発掘1自体にはシナジーは期待できないが、単純に毎ターン使い回せる粉砕ということ自体が使いやすく強い。ここ最近勢力を伸ばしているポスト系やストンピィ系にサイドから入れてマナ基盤をズタボロにできる。古の遺恨と違い緑マナを要求しないので、緑を使わないデッキで納墓からのサーチ先としても優秀。
8、陰謀団の療法士
これはモダンホライゾンが発表した際に公開された時に書いた以前の日記の通り。
能力のタイミングに制限があるのが難点ではあるものの、ゾンバードメントではハンデス・サクり台・ディスカード手段の三役を1枚でこなせるので試してみたい。
9、終異種
変異種の亜種がついに黒で登場。
威迫・接死と+1/-1・-1/+1能力が非常に相性が良く、実質的にかなりブロックされにくい回避能力となっている上に、ブロックで討ち取られても2対1交換を強制できて不死によって復活できるし、4/4になって帰ってくるので+1/-1・-1/+1能力が更に活きるということもあり、個々の能力がそれぞれ非常に噛み合っているため戦闘においてはかなりの制圧力があると言える。
しかし除去耐性として見た場合の不死は、復活が1回きりであるということ、ソープロやバウンスには無力で元々火力耐性もあり破壊やマイナス修正除去以外にはあまり意味がないという側面もあるので、他の亜種と比べたら信頼性は薄いのが難点ではある。
これ自体4マナと重いので、黒ストンピィで高速召喚して苦手な除去はチャリスで補いたい。
10、疫病を仕組むもの
生物に仕組まれた疫病が内蔵され、更に対戦相手にしか影響しなくなっただけでもかなり優秀なのに、自身に接死まで付いているという大盤振る舞いはすごい。生物なので除去されやすいものの、タフ1をシャットアウトしつつクロックを刻み大型生物にも戦闘で対処できるので、使い勝手はかなり良さそう。
同じマナコストで似たような生物に疫病吐きがいるが、こちらも決して悪くはないものの自分の生物にもダメージが飛ぶためトークン戦略が取れず構築の幅が狭まってしまうが、疫病を仕組むものならなんら問題ない。
個人的には終異種と同様黒ストンピィでの採用が本命。苦手なネメシスやヤンパイに対応できてマルドゥの急襲指揮者との併用も可能になったので、かなり強化されるのではないか。
11、スランの医師、ヨーグモス
またしても黒ストンピィ要員の候補。
サクり台能力がマナいらずで戦場に直接触れてアドまで取れる能力なので、前述のような黒ストンピィでトークン戦略を取れるような構築をすればかなりの盤面制圧力を持つことができる。終異種と併用すれば、不死によって乗った+1/+1カウンターと-1/-1カウンターを相殺させ何度でも不死を利用する、ということも可能。
増殖の能力は単体では1/-1カウンターを増殖する以外使い道はないが、PWと併用するなどして自然に活かせられる構築をして利用したい。
12、ゴブリンの技師
起動型能力はゴブリンの溶接工とはマナがかかったり交換ではなく生贄がコストだったりと細かな違いはあるが、ペインターにおけるチャリスに引っかからないサーチできる溶接工としての採用が真っ先に考えられる。
またはグリクシステゼレットのソプターコンボのサーチとして、弱者の剣を直接墓地にサーチできるのが強いし、鋳造所も生きてターンが返れば自身でリアニメイトできるので足りない方を補うコンボの潤滑油として使えそう。
13、パシャリク・モンス
ゴブリンストンピィに入れたい1枚。12ラブルでトークンを大量生産して、戦闘でトークンが死んでも1点飛ばせるようになることでタフ2以上も対処できるように。
トークン生成能力も上記の能力と噛み合っており、更に自身もサクれるので伝説も気にならない。
14、悪ふざけ
発掘1自体にはシナジーは期待できないが、単純に毎ターン使い回せる粉砕ということ自体が使いやすく強い。ここ最近勢力を伸ばしているポスト系やストンピィ系にサイドから入れてマナ基盤をズタボロにできる。古の遺恨と違い緑マナを要求しないので、緑を使わないデッキで納墓からのサーチ先としても優秀。
モダンホライゾンのフルスポイラーが解禁されました。
特殊セットは今まで特に注目カードを挙げていませんでしたが、他の特殊セットと比べて新規カードが圧倒的に多く逆に再録が少ないのと、モダンにテコ入れするためにスタンダードでは収録や再録できないぐらいのパワーを持つカードを収録するというのがコンセプトのため、レガシーにも十分影響があると考えられるので今回は注目カードを挙げていきたいなと思います。
一通り確認したところ、灯争大戦以上に使ってみたいと思ったカードが出てきましたので、今回またしても複数回に分けて挙げていきます。
1、美徳の力
白のピッチスペルだが唯一場に残るエンチャントなので、ダメージや修正による除去耐性を恒久的に得つつ生物全体を強化できるので、ピッチで撃ってもディスアドをものともしない働きが期待できる。
デスタクに採用すれば、2枚目以降は腐りやすい伝説生物を気兼ねなくピッチに利用できるし、自分のサリアの影響を受けてもピッチで撃てばたった1マナなのでテンポの影響はほとんどない。
全体1点火力や夜の戦慄や硫黄の精霊、湿地での被災等のマイナス修正対策としてサイドの萎れ葉の代わりになるのはもちろん、全体強化が単純に強いのでメインからでも1〜2枚忍ばせても良さそう。
2、ルーンの与え手
本家ルーンの母と比べると自身を対象に取れないのが致命的に劣る部分だが、タフネスが2に上がったのとプロテクション無色を得られるようになったという本家にはないメリットも存在するので、5枚目のルーンの母枠として取る価値はそれなりにありそう。
しかし本家同様自分の生物にしか対象に取れないので当時の怨恨よろしく相手の装備品を剥がすという使い道はできないし、逆に装備している自分の生物にプロテクション無色を与えると剥がれてしまうので注意。
3、バザールの交易魔道士
マナコスト的に青ストンピィに採用してみたい一枚。
ディスカード手段の能力をうまく利用できるような構築にすれば稲妻圏外で回避能力もあるこれはCPが高く優秀。例えば後述の注目カードである永劫のこだまのような強烈なFB呪文を落としたりしてディスアドを一気に取り返しすような使い方などして運用したい。
逆にディスカード手段が噛み合わないとハンドアドを失う生物にしては物足りないスペックと成り下がってしまうが、ハンドが0枚の時に出せば能力を利用できなくてもアドは失わないので、最悪ディスアドすることなく出せると考えれば良しか。
4、永劫のこだま
Timetwisterの亜種。時のらせん等の亜種も存在するが、これは墓地にさえ落とせば本家と全く同じコストや性能なのが嬉しい。ナーセットやレオヴォルドとのお手軽コンボもあるが、やはりメインは一日のやり直しと違い瞬殺コンボとしての利用できるという部分を考えたい。
墓地に落とす方法はレガシーならルーティングや集団的蛮行等のディスカード手段の他、納墓や直感で簡単に落とすことができるので使いやすい。もしハンドにあった場合はLEDで処理し捻出した3マナをそのまま使って唱えられるのでコンボデッキで非常に利用しやすい(しかもLEDはマナ能力なので仮に相手にサージカルを握られていてもこれを即FBすれば追放される隙がないし、納墓やルーティングで利用する際も同様に即FBできればOK)。
もしハイタイドなどの青単で組むとしたらナーセットとのコンボも一緒に組み込んで相手のハンドを枯らせつつ安全にコンボを決めるという使い方をしたり、納墓やルーティングを利用した新しい形のストーム系コンボの可能性を模索中。
5、否定の力
ほとんどの場合劣化版の意志の力なので、レガシーではほとんど採用されることないと思うが、続唱のようなピッチ以外の打ち消しが取れないようなデッキの場合はコンボ対策としてサイドから5枚目以降の意志の力としての採用は考えられる。
6、捧げ物の魔道士
アーティファクトには強力な2マナ域のカードが多いので、そこにアクセスできるようになったのは大きい。
青ストンピィで十手を持ってくるのは最もベーシックな利用法だが、他にもソプターコンボを狙う場合はどちらもこれでサーチできるようになったのでかなり決めやすくなる。
7、最高工匠卿、ウルザ
アンティキティーストンピィに入れてみたい1枚。ダブシンなのはやや重いが、ウルザの後継、カーンの-2能力と同じcipを持つので攻守に優れ、マナ能力と束の間の開口能力が噛み合いアドも得られるので盤面をひっくり返す能力も秘めている。
タップしても能力が持続する妨害手段(チャリスやるつぼ+不毛、罠の橋など)をうまく利用したい。
特殊セットは今まで特に注目カードを挙げていませんでしたが、他の特殊セットと比べて新規カードが圧倒的に多く逆に再録が少ないのと、モダンにテコ入れするためにスタンダードでは収録や再録できないぐらいのパワーを持つカードを収録するというのがコンセプトのため、レガシーにも十分影響があると考えられるので今回は注目カードを挙げていきたいなと思います。
一通り確認したところ、灯争大戦以上に使ってみたいと思ったカードが出てきましたので、今回またしても複数回に分けて挙げていきます。
1、美徳の力
白のピッチスペルだが唯一場に残るエンチャントなので、ダメージや修正による除去耐性を恒久的に得つつ生物全体を強化できるので、ピッチで撃ってもディスアドをものともしない働きが期待できる。
デスタクに採用すれば、2枚目以降は腐りやすい伝説生物を気兼ねなくピッチに利用できるし、自分のサリアの影響を受けてもピッチで撃てばたった1マナなのでテンポの影響はほとんどない。
全体1点火力や夜の戦慄や硫黄の精霊、湿地での被災等のマイナス修正対策としてサイドの萎れ葉の代わりになるのはもちろん、全体強化が単純に強いのでメインからでも1〜2枚忍ばせても良さそう。
2、ルーンの与え手
本家ルーンの母と比べると自身を対象に取れないのが致命的に劣る部分だが、タフネスが2に上がったのとプロテクション無色を得られるようになったという本家にはないメリットも存在するので、5枚目のルーンの母枠として取る価値はそれなりにありそう。
しかし本家同様自分の生物にしか対象に取れないので当時の怨恨よろしく相手の装備品を剥がすという使い道はできないし、逆に装備している自分の生物にプロテクション無色を与えると剥がれてしまうので注意。
3、バザールの交易魔道士
マナコスト的に青ストンピィに採用してみたい一枚。
ディスカード手段の能力をうまく利用できるような構築にすれば稲妻圏外で回避能力もあるこれはCPが高く優秀。例えば後述の注目カードである永劫のこだまのような強烈なFB呪文を落としたりしてディスアドを一気に取り返しすような使い方などして運用したい。
逆にディスカード手段が噛み合わないとハンドアドを失う生物にしては物足りないスペックと成り下がってしまうが、ハンドが0枚の時に出せば能力を利用できなくてもアドは失わないので、最悪ディスアドすることなく出せると考えれば良しか。
4、永劫のこだま
Timetwisterの亜種。時のらせん等の亜種も存在するが、これは墓地にさえ落とせば本家と全く同じコストや性能なのが嬉しい。ナーセットやレオヴォルドとのお手軽コンボもあるが、やはりメインは一日のやり直しと違い瞬殺コンボとしての利用できるという部分を考えたい。
墓地に落とす方法はレガシーならルーティングや集団的蛮行等のディスカード手段の他、納墓や直感で簡単に落とすことができるので使いやすい。もしハンドにあった場合はLEDで処理し捻出した3マナをそのまま使って唱えられるのでコンボデッキで非常に利用しやすい(しかもLEDはマナ能力なので仮に相手にサージカルを握られていてもこれを即FBすれば追放される隙がないし、納墓やルーティングで利用する際も同様に即FBできればOK)。
もしハイタイドなどの青単で組むとしたらナーセットとのコンボも一緒に組み込んで相手のハンドを枯らせつつ安全にコンボを決めるという使い方をしたり、納墓やルーティングを利用した新しい形のストーム系コンボの可能性を模索中。
5、否定の力
ほとんどの場合劣化版の意志の力なので、レガシーではほとんど採用されることないと思うが、続唱のようなピッチ以外の打ち消しが取れないようなデッキの場合はコンボ対策としてサイドから5枚目以降の意志の力としての採用は考えられる。
6、捧げ物の魔道士
アーティファクトには強力な2マナ域のカードが多いので、そこにアクセスできるようになったのは大きい。
青ストンピィで十手を持ってくるのは最もベーシックな利用法だが、他にもソプターコンボを狙う場合はどちらもこれでサーチできるようになったのでかなり決めやすくなる。
7、最高工匠卿、ウルザ
アンティキティーストンピィに入れてみたい1枚。ダブシンなのはやや重いが、ウルザの後継、カーンの-2能力と同じcipを持つので攻守に優れ、マナ能力と束の間の開口能力が噛み合いアドも得られるので盤面をひっくり返す能力も秘めている。
タップしても能力が持続する妨害手段(チャリスやるつぼ+不毛、罠の橋など)をうまく利用したい。
灯争大戦参入後のURデルバー構築
2019年5月26日 Magic: The Gathering灯争大戦が発売してしばらく経ちましたが、前評判通りレガシーに与える影響はかなり大きく、多数の新カードが早速猛威を振るっています。
さて、URデルバーにとっては危険因子やプテラマンダー、舞台照らしなどここ最近では採用を検討できるようなカードをコンスタントにもらっていますが、灯争大戦においても期待の新人である戦慄衆の秘儀術師がやはり前評判通り早速使われ始めています。
ブレストや稲妻をノーコストで使い回す動きが単純に強く、ターンが帰ればボブ以上にテンポも良く質のいいアドバンテージを稼いでくれるため、ヤンパイに代わる新四天王としての呼び声も高まってきています。
今回の日記では、そんな秘儀術師のポテンシャルを更に引き出すべく、ギタ調禁止前のURデルバーでも使用していた執着的探訪を、秘儀術師を採用したURデルバーに組み込んでみてはどうかということを考察したいと思います。
執着的探訪の有用性については以前にギタ調禁止前の日記でも説明しましたが、果敢型URデルバーに組み込むことで単体でもそれなりに強力だったものの、ギタ調が禁止になってからはフィズる可能性が高くなってしまったのと、代わりのアドバンテージ源である舞台照らしを試していたということもあり、長らく採用を見送っていました。
しかし、秘儀術師に執着的探訪が付くことで様々なメリットが生まれ、フィズるデメリットを押してでも使いたい理由が出てきました。
まず、恒久的な+1/+1修正がURデルバーでは完全な死に能力であるトランプルが活き、執着的探訪のドロー能力を存分に発揮できます。
例えばヤンパイやリンリンなどのトークンなどによるチャンプによるドロー阻止を許しません。更に秘儀術師のタフネス3というサイズが最も活きるのが対ネメシス戦です。1/3のままでは一度使い回しをするだけで犬死してしまうところを2/4になることでネメシスのブロックをものともせず悠々と攻撃ができて、更にトランプルでしっかりドローまでできるのです。
ミラーマッチやグリクシスデルバー相手にも火力による除去耐性が付くので、場持ちも良くなりアドを稼げる回数が増えるというのも大きなメリット。
また、パワーが上がることでコストが2までの呪文も使い回すことが可能になったので、削剥や発展の代価などの複数枚取りづらい呪文もノーコストで使い回せるというのが非常に強力な動きになります。
テンポデッキが秘儀術師のおかげて自然にアドを稼げるようになっただけでもすばらしいですが、そこから執着的探訪を付けることができれば、もはやテンポデッキとは思えないほどのアドを生み出し相手を圧倒できるようになります。
以上を踏まえ、果敢型の新生URデルバーを構築してみました。
4秘密を掘り下げるもの
4僧院の速槍
4戦慄衆の秘儀術師
2真の名の宿敵
14
4渦まく知識
4思案
2定業
4執着的探訪
4稲妻
4稲妻の連鎖
4目くらまし
4意志の力
30
3Volcanic Island
2島
1山
4沸騰する小湖
4霧深い雨林
2乾燥大地
16
SB
1破壊放題
1削剥
1ゴブリンのクレーター掘り
1電弧の痕跡
1イゼットの静電術師
1発展の代価
2外科的摘出
2紅蓮破
2大歓楽の幻霊
1高山の月
1カラカス
15
基本的な動きは、以前にギタ調禁止前の果敢型URデルバーで採用した日記で説明したのとほぼ変わらずですが、今回は秘儀術師との相性を考え執着的探訪をフル投入で調整しています。本来なら秘儀術師と相性のいいヤンパイも採用したいところですが、執着的探訪のエンチャント先としては不向きなため、果敢型では止むを得ず採用を見送ることにります。
サイドについてですが、まず高山の月とカラカスは、URデルバーが最も苦手なターボデプスの対策です。カラカスの代わりには蒸気の絡みつきも考えましたが、対アンコウやタルモにもそれなりに有効なものの、稲妻と秘儀術師があれば焼くことができるのでそこまで重要ではなく、それならショーテルのエムラにも対応できなる点と苦手なデスタクのサリアを退ける役割も兼ねている方がサイドカードとしては幅が広く対策しづらいのでカラカスを優先しました。
次に破壊放題ですが、秘儀術師と抜群の相性を誇ります。1マナなので当然使い回しが効き、そこから複製で複数枚の置物に対処できるようになっている他、本来引っかかるチャリスに対しても複製で割ることができるので、置物対策としては最高の相棒となってくれるでしょう。
大歓楽の幻霊についてはコンボやコントロール対策ですが、狼狽の嵐にしないのは果敢型という前のめりなデッキのため打ち消しを構える動きが強くないというのと、執着的探訪のエンチャント先としても使える生物という面があるためこちらを優先しています。
とりあえずはこの構築が基本の形になりますが、ポスト系のデッキが増えている傾向にあるので、メタに合わせて定業もしくは執着的探訪の枠をメインから削剥や発展の代価を投入したりして柔軟に考え、次回大会に参加する際は早速これを持ち込んで試してみたいと思います。
さて、URデルバーにとっては危険因子やプテラマンダー、舞台照らしなどここ最近では採用を検討できるようなカードをコンスタントにもらっていますが、灯争大戦においても期待の新人である戦慄衆の秘儀術師がやはり前評判通り早速使われ始めています。
ブレストや稲妻をノーコストで使い回す動きが単純に強く、ターンが帰ればボブ以上にテンポも良く質のいいアドバンテージを稼いでくれるため、ヤンパイに代わる新四天王としての呼び声も高まってきています。
今回の日記では、そんな秘儀術師のポテンシャルを更に引き出すべく、ギタ調禁止前のURデルバーでも使用していた執着的探訪を、秘儀術師を採用したURデルバーに組み込んでみてはどうかということを考察したいと思います。
執着的探訪の有用性については以前にギタ調禁止前の日記でも説明しましたが、果敢型URデルバーに組み込むことで単体でもそれなりに強力だったものの、ギタ調が禁止になってからはフィズる可能性が高くなってしまったのと、代わりのアドバンテージ源である舞台照らしを試していたということもあり、長らく採用を見送っていました。
しかし、秘儀術師に執着的探訪が付くことで様々なメリットが生まれ、フィズるデメリットを押してでも使いたい理由が出てきました。
まず、恒久的な+1/+1修正がURデルバーでは完全な死に能力であるトランプルが活き、執着的探訪のドロー能力を存分に発揮できます。
例えばヤンパイやリンリンなどのトークンなどによるチャンプによるドロー阻止を許しません。更に秘儀術師のタフネス3というサイズが最も活きるのが対ネメシス戦です。1/3のままでは一度使い回しをするだけで犬死してしまうところを2/4になることでネメシスのブロックをものともせず悠々と攻撃ができて、更にトランプルでしっかりドローまでできるのです。
ミラーマッチやグリクシスデルバー相手にも火力による除去耐性が付くので、場持ちも良くなりアドを稼げる回数が増えるというのも大きなメリット。
また、パワーが上がることでコストが2までの呪文も使い回すことが可能になったので、削剥や発展の代価などの複数枚取りづらい呪文もノーコストで使い回せるというのが非常に強力な動きになります。
テンポデッキが秘儀術師のおかげて自然にアドを稼げるようになっただけでもすばらしいですが、そこから執着的探訪を付けることができれば、もはやテンポデッキとは思えないほどのアドを生み出し相手を圧倒できるようになります。
以上を踏まえ、果敢型の新生URデルバーを構築してみました。
4秘密を掘り下げるもの
4僧院の速槍
4戦慄衆の秘儀術師
2真の名の宿敵
14
4渦まく知識
4思案
2定業
4執着的探訪
4稲妻
4稲妻の連鎖
4目くらまし
4意志の力
30
3Volcanic Island
2島
1山
4沸騰する小湖
4霧深い雨林
2乾燥大地
16
SB
1破壊放題
1削剥
1ゴブリンのクレーター掘り
1電弧の痕跡
1イゼットの静電術師
1発展の代価
2外科的摘出
2紅蓮破
2大歓楽の幻霊
1高山の月
1カラカス
15
基本的な動きは、以前にギタ調禁止前の果敢型URデルバーで採用した日記で説明したのとほぼ変わらずですが、今回は秘儀術師との相性を考え執着的探訪をフル投入で調整しています。本来なら秘儀術師と相性のいいヤンパイも採用したいところですが、執着的探訪のエンチャント先としては不向きなため、果敢型では止むを得ず採用を見送ることにります。
サイドについてですが、まず高山の月とカラカスは、URデルバーが最も苦手なターボデプスの対策です。カラカスの代わりには蒸気の絡みつきも考えましたが、対アンコウやタルモにもそれなりに有効なものの、稲妻と秘儀術師があれば焼くことができるのでそこまで重要ではなく、それならショーテルのエムラにも対応できなる点と苦手なデスタクのサリアを退ける役割も兼ねている方がサイドカードとしては幅が広く対策しづらいのでカラカスを優先しました。
次に破壊放題ですが、秘儀術師と抜群の相性を誇ります。1マナなので当然使い回しが効き、そこから複製で複数枚の置物に対処できるようになっている他、本来引っかかるチャリスに対しても複製で割ることができるので、置物対策としては最高の相棒となってくれるでしょう。
大歓楽の幻霊についてはコンボやコントロール対策ですが、狼狽の嵐にしないのは果敢型という前のめりなデッキのため打ち消しを構える動きが強くないというのと、執着的探訪のエンチャント先としても使える生物という面があるためこちらを優先しています。
とりあえずはこの構築が基本の形になりますが、ポスト系のデッキが増えている傾向にあるので、メタに合わせて定業もしくは執着的探訪の枠をメインから削剥や発展の代価を投入したりして柔軟に考え、次回大会に参加する際は早速これを持ち込んで試してみたいと思います。
今回は3回に渡りましたが、これで灯争大戦の注目カードは最後です。
もう本日発売に迫っているのでギリギリアウトかもしれませんが、急いで挙げ切りたいと思います。
12、夢を引き裂く者、アショク
黒を含む混成マナなので暗黒の儀式から1ターン目に出すことができれば、フェッチを腐らせられることで強力なマナ拘束力を発揮できる。リアニ相手にはフェッチと納墓を禁止しつつ-1能力で墓地掃除も兼ねるのでありがたい。しかしどの能力も場の戦況には何も影響を与えないので場持ちは悪く、出るのが少しでも遅くなれば間に合わず一気に弱くなってしまうのが難点。
13、支配の片腕、ドビン
アメ棘のようなコスト増加の常在型能力を持つPW。範囲は狭まっているが、エンチャントやPWは元々数が少ないので、対コンボやコントロールの拘束力としては十分効果を発揮できそう。
青系ストンピィでは自分でもWillを使いたいことが多いため、三球のような全体に被害が及ぶ置物は使い辛く他に選択肢がなかったが、これでようやく1ターン目から出せる選択肢ができたのが非常に嬉しい。-1能力はあくまで時間稼ぎだけの能力だが、それで自身も守れて最大5回も使えるので思った以上に硬そう。アンティキティーストンピィでは、アンティキティー戦争のⅢに到達するまでの時間稼ぎとして正にうってつけ。
14、時を解すもの、テフェリー
奇跡や青白系石鍛冶が主に対コントロール用のサイドとして使われそうなPW。常在型能力のおかげで打ち消しや除去を気にせずフィニッシャーを安全に着地することができる。
+1能力は、特に奇跡で使うと思案を相手のターンに撃って終末を奇跡したり相手の動きを見てから相殺の積み込みができるなど、独楽を彷彿とさせるようないやらしい動きができるのでデッキに合っている。
-3能力はソーサリータイミングだが3マナで範囲の広い排撃を撃ちながら場に残ると考えたらCPは上々で、最低でもドローだけはできるので基本的にはメインに入れても腐ることはないが、デルバー系相手や常在型能力の方があまり効かないデッキに対してはやや重いので、採用枚数は抑えた方が良さそう。
15、崇高な高匠、サヒーリ
青単色でも使えるヤンパイ(もしくは果敢のないメンター)とも言えるPW。
単純に赤青系の中速〜コントロール寄りのデッキのフィニッシャー候補にもなるが、それならより軽いヤンパイでいいため、できれば-2能力を活かせられる構成で使用したいが今の所コレという使い道は思いついていない。しかし何かやらかしてくれそうなので現在考案中。
ダブシンなのがネックだが、0マナアーティファクトと相性がいいのでアンティキティー戦争を入れた青ストンピィに入れて追加のサイ枠にしたい。
16、爆発域
0マナアーティファクトやトークンには対処できないものの、漸増爆弾が土地になったことでデッキに入る幅が大きく広がった。レガシーではもみ消し以外では打ち消されないというメリットも後押しして、万能除去としてあらゆるデッキのメインからの採用が十分考えられる。
例えばPOXや青黒系・赤青系コントロールのようなエンチャントを破壊できない色のデッキでもわざわざサイドに漸増爆弾を取らなくてもよくなるのが強化点となり、土地単でも使い回しの効く漸増爆弾を得たことでコントロール力が更にアップ。輪作から持ってこれるので1枚挿しでも十分運用できる。エルドラージストンピィやポスト系・MUDでは色マナの基盤を一切壊すことなくメインから生物や置物に対応できるようになった。前者はダメージレースを制しやすく後者は時間稼ぎになるのでどちらもマッチしている。
ただしあくまで土地なので、土地単では一番割りたい月やBtBのような土地対策にはまとめて引っかかってしまうので過信は禁物ではある。
もう本日発売に迫っているのでギリギリアウトかもしれませんが、急いで挙げ切りたいと思います。
12、夢を引き裂く者、アショク
黒を含む混成マナなので暗黒の儀式から1ターン目に出すことができれば、フェッチを腐らせられることで強力なマナ拘束力を発揮できる。リアニ相手にはフェッチと納墓を禁止しつつ-1能力で墓地掃除も兼ねるのでありがたい。しかしどの能力も場の戦況には何も影響を与えないので場持ちは悪く、出るのが少しでも遅くなれば間に合わず一気に弱くなってしまうのが難点。
13、支配の片腕、ドビン
アメ棘のようなコスト増加の常在型能力を持つPW。範囲は狭まっているが、エンチャントやPWは元々数が少ないので、対コンボやコントロールの拘束力としては十分効果を発揮できそう。
青系ストンピィでは自分でもWillを使いたいことが多いため、三球のような全体に被害が及ぶ置物は使い辛く他に選択肢がなかったが、これでようやく1ターン目から出せる選択肢ができたのが非常に嬉しい。-1能力はあくまで時間稼ぎだけの能力だが、それで自身も守れて最大5回も使えるので思った以上に硬そう。アンティキティーストンピィでは、アンティキティー戦争のⅢに到達するまでの時間稼ぎとして正にうってつけ。
14、時を解すもの、テフェリー
奇跡や青白系石鍛冶が主に対コントロール用のサイドとして使われそうなPW。常在型能力のおかげで打ち消しや除去を気にせずフィニッシャーを安全に着地することができる。
+1能力は、特に奇跡で使うと思案を相手のターンに撃って終末を奇跡したり相手の動きを見てから相殺の積み込みができるなど、独楽を彷彿とさせるようないやらしい動きができるのでデッキに合っている。
-3能力はソーサリータイミングだが3マナで範囲の広い排撃を撃ちながら場に残ると考えたらCPは上々で、最低でもドローだけはできるので基本的にはメインに入れても腐ることはないが、デルバー系相手や常在型能力の方があまり効かないデッキに対してはやや重いので、採用枚数は抑えた方が良さそう。
15、崇高な高匠、サヒーリ
青単色でも使えるヤンパイ(もしくは果敢のないメンター)とも言えるPW。
単純に赤青系の中速〜コントロール寄りのデッキのフィニッシャー候補にもなるが、それならより軽いヤンパイでいいため、できれば-2能力を活かせられる構成で使用したいが今の所コレという使い道は思いついていない。しかし何かやらかしてくれそうなので現在考案中。
ダブシンなのがネックだが、0マナアーティファクトと相性がいいのでアンティキティー戦争を入れた青ストンピィに入れて追加のサイ枠にしたい。
16、爆発域
0マナアーティファクトやトークンには対処できないものの、漸増爆弾が土地になったことでデッキに入る幅が大きく広がった。レガシーではもみ消し以外では打ち消されないというメリットも後押しして、万能除去としてあらゆるデッキのメインからの採用が十分考えられる。
例えばPOXや青黒系・赤青系コントロールのようなエンチャントを破壊できない色のデッキでもわざわざサイドに漸増爆弾を取らなくてもよくなるのが強化点となり、土地単でも使い回しの効く漸増爆弾を得たことでコントロール力が更にアップ。輪作から持ってこれるので1枚挿しでも十分運用できる。エルドラージストンピィやポスト系・MUDでは色マナの基盤を一切壊すことなくメインから生物や置物に対応できるようになった。前者はダメージレースを制しやすく後者は時間稼ぎになるのでどちらもマッチしている。
ただしあくまで土地なので、土地単では一番割りたい月やBtBのような土地対策にはまとめて引っかかってしまうので過信は禁物ではある。
もう発売がもうすぐに迫っていますが、前回に引き続き、灯争大戦の注目カードを挙げていきます。
6、猪の祟神、イルハグ
伝説と言えど赤が5マナ6/6トランプル+除去耐性持ちの時点でマナレシオが高いのにビックリだが、特筆すべきは攻撃時の能力。いわゆる騙し討ちに似た踏み倒し能力を内蔵しているため赤単スニークにおける発射台の追加枠として、煮えたぎる歌から出してハンドのグリセルや赤タイタンを踏み倒したい。エムラだと滅殺が誘発しないのが残念だが、イルハグと一緒に殴ればほぼ勝ちなのでそこまで気にする必要もないかもしれない。素出しできる安定性を重視するなら赤機械巨人を採用したり、ハンドに戻った時も誘発する隔離するタイタンのような生物を使うのもアリか。
7、ブリキ通りの重鎮、クレンコ
軍勢の戦親分に続き、またしてもラブル枠が追加。先輩2種類と違い出たターンにトークンは出ない上に攻撃しないといけないが、自身がどんどん大きくなるので戦闘や火力では多少死ににくくはなっている。
他のパンプ能力と相性が良く、例えば軍勢の戦親分と併用すると、教導でパンプした後に自身の能力でパンプすればトークンが一気に3つ出てくるし、ゴブリンの酋長だとロード能力と速攻が非常に相性がいい。他にも血染めの月と元祖ゴブリンの王で山渡を得れば、クレンコ本体の序盤の戦闘の弱さをカバーできるので、ゴブリンストンピィに組み込みたい。
8、破滅の終焉
1マナ重くなった分緑以外の生物も持ってこれるようになった汎用性上がった緑頂点。
ただし緑が濃くなってしまった分、多色かつマナ加速ができるデッキで使うとなるとかなり制限がかかるため、結局エルフの追加の緑頂点の枠に収まってしまいそう。
緑系ポストにはギリギリ入れられそうではあるので、破滅の終焉からエルドラージを引っ張ってきて緑頂点との差別化を図ろう。
9、自然への回帰
帰化の上位互換。追加された墓地対策追加のモードは最低限のものだが、サイドの枠が少しでも減らせるもしくは墓地対策が増やせるのはやはり魅力。墓地対策としては2マナは重いが、緑ストンピィならモックスと併用で即使えるしチャリスにも引っかからない。
10、野獣の擁護者、ビビアン
緑ストンピィに是非採用したい1枚。シングルシンボル3マナで+能力を持っているPWというのはこれだけなので、1ターン目から高確率で出せるPWはなかなかの脅威ではないだろうか。
−2で常に生物を瞬速で出るプレッシャーを与えつつ+1で攻めながら自身を守れるので、対デルバー系にもコントロール系にも能力を発揮でき、場持ちもかなり期待できそう。
11、アングラスの暴力
アーティファクトも処理できるようになった戦慄掘りのようなカード。
対象を取っていないのは一長一短の部分はあるが、基本的にレガシーは置物もPWも少数精鋭なので撃ち漏らす心配はほとんどなく、ネメシスを処理できるのはかなり重要なので、戦慄掘りと比べてグリコンのようなデッキでは十分メインから採用されそう。
ネメシス・神ジェイス・装備品に対応していることから、これで最近トップメタの青白系石鍛冶を引きずり下ろしたい。
6、猪の祟神、イルハグ
伝説と言えど赤が5マナ6/6トランプル+除去耐性持ちの時点でマナレシオが高いのにビックリだが、特筆すべきは攻撃時の能力。いわゆる騙し討ちに似た踏み倒し能力を内蔵しているため赤単スニークにおける発射台の追加枠として、煮えたぎる歌から出してハンドのグリセルや赤タイタンを踏み倒したい。エムラだと滅殺が誘発しないのが残念だが、イルハグと一緒に殴ればほぼ勝ちなのでそこまで気にする必要もないかもしれない。素出しできる安定性を重視するなら赤機械巨人を採用したり、ハンドに戻った時も誘発する隔離するタイタンのような生物を使うのもアリか。
7、ブリキ通りの重鎮、クレンコ
軍勢の戦親分に続き、またしてもラブル枠が追加。先輩2種類と違い出たターンにトークンは出ない上に攻撃しないといけないが、自身がどんどん大きくなるので戦闘や火力では多少死ににくくはなっている。
他のパンプ能力と相性が良く、例えば軍勢の戦親分と併用すると、教導でパンプした後に自身の能力でパンプすればトークンが一気に3つ出てくるし、ゴブリンの酋長だとロード能力と速攻が非常に相性がいい。他にも血染めの月と元祖ゴブリンの王で山渡を得れば、クレンコ本体の序盤の戦闘の弱さをカバーできるので、ゴブリンストンピィに組み込みたい。
8、破滅の終焉
1マナ重くなった分緑以外の生物も持ってこれるようになった汎用性上がった緑頂点。
ただし緑が濃くなってしまった分、多色かつマナ加速ができるデッキで使うとなるとかなり制限がかかるため、結局エルフの追加の緑頂点の枠に収まってしまいそう。
緑系ポストにはギリギリ入れられそうではあるので、破滅の終焉からエルドラージを引っ張ってきて緑頂点との差別化を図ろう。
9、自然への回帰
帰化の上位互換。追加された墓地対策追加のモードは最低限のものだが、サイドの枠が少しでも減らせるもしくは墓地対策が増やせるのはやはり魅力。墓地対策としては2マナは重いが、緑ストンピィならモックスと併用で即使えるしチャリスにも引っかからない。
10、野獣の擁護者、ビビアン
緑ストンピィに是非採用したい1枚。シングルシンボル3マナで+能力を持っているPWというのはこれだけなので、1ターン目から高確率で出せるPWはなかなかの脅威ではないだろうか。
−2で常に生物を瞬速で出るプレッシャーを与えつつ+1で攻めながら自身を守れるので、対デルバー系にもコントロール系にも能力を発揮でき、場持ちもかなり期待できそう。
11、アングラスの暴力
アーティファクトも処理できるようになった戦慄掘りのようなカード。
対象を取っていないのは一長一短の部分はあるが、基本的にレガシーは置物もPWも少数精鋭なので撃ち漏らす心配はほとんどなく、ネメシスを処理できるのはかなり重要なので、戦慄掘りと比べてグリコンのようなデッキでは十分メインから採用されそう。
ネメシス・神ジェイス・装備品に対応していることから、これで最近トップメタの青白系石鍛冶を引きずり下ろしたい。
灯争大戦のフルスポイラーが発表されました。
今回はPWにスポットを当てていて非常に種類が多いセットになっています。
常在型能力を持っていたり+能力のない使い捨てもしくはエンチャントのような使い勝手にデザインされていたりと面白く、こういった新しい形は個人的にも意欲が非常に湧いてきています。
もちろんPW以外にも面白そうなカードもたくさんありますが注目しているのは今回かなり多いので、数回に分けて挙げていきたいと思います。
1高名な弁護士、トミク
土地に対するヘイト能力を内蔵した伝説の生物。用途としては不毛やリシャポ、シンクホールのような土地拘束から守る、るつぼやロームを封じる、演劇の舞台を封じDDコンボなどを妨害できる、自分のミシュランが被覆を得られるなどが挙げられる。更にタフネス3で罰火にも耐えられるのがいかにも対土地単を意識したスペック。
護衛募集院でサーチができなかったり伝説だったりと一長一短な部分は多いが、メインで入れるとしたらコストやスペック的にセラの報復者と入れ替わりになりそう。
2、覆いを割く者、ナーセット
対戦相手だけに迷宮の霊魂の能力を内蔵したPW。3マナでこちらはアドを取り相手のドローを封じるという動きは、殴れないレオヴォルドのような使い勝手になりそう。主に青系のコントロールミラーでのサイド候補として。
3、リリアナの勝利
ついに悪魔の布告のほぼ上位互換が登場。グリコンではラスアナを使うので布告と完全に入れ替わりで白力線をものともしないのが素晴らしい。
ヴェリアナ・ラスアナを両方取った黒の濃いリリアナコンを組んでみたい。
4、戦慄衆の秘儀術師
トランプルを持っているのに1/3というスペックがミスマッチだが、単純にブレストや稲妻をコストも払わず使い回すだけでも十分強く、生き残ればボブのような使い勝手になりそう。祖先の幻視のような待機呪文を墓地から踏み倒せるのは魅力的なので、その辺りもうまく組み合わせた構築をしたい。
トランプルを活かすには強大化にようなカードでパンプしつつ墓地からもう一度強大化して大ダメージを狙ったり、もしくはウィザードなのでエイデリズでパンプして2〜3マナ域までの呪文を踏み倒す使い方が現実的か。
5、約束の終焉
赤のダブシンという色拘束がキツイので入るデッキは限定されるが、X=1で十分な威力を発揮でき、単純にバーンに入れても3マナで稲妻+チェンライの6点火力として見れば悪くない。戦慄衆の秘儀術師と同様、待機呪文を踏み倒せるのはやはり魅力的なので、できればそれも活かせた構築をしたい。
1枚で合計3つの呪文を唱えられることから、弧光のフェニックスを復活させるためにはおあつらえ向き。URカラーで、ルーティングで祖先の幻視やフェニックスを落とし、これで3ドローしつつフェニックスを復活させるようなデッキを組んでみたい。
今回はPWにスポットを当てていて非常に種類が多いセットになっています。
常在型能力を持っていたり+能力のない使い捨てもしくはエンチャントのような使い勝手にデザインされていたりと面白く、こういった新しい形は個人的にも意欲が非常に湧いてきています。
もちろんPW以外にも面白そうなカードもたくさんありますが注目しているのは今回かなり多いので、数回に分けて挙げていきたいと思います。
1高名な弁護士、トミク
土地に対するヘイト能力を内蔵した伝説の生物。用途としては不毛やリシャポ、シンクホールのような土地拘束から守る、るつぼやロームを封じる、演劇の舞台を封じDDコンボなどを妨害できる、自分のミシュランが被覆を得られるなどが挙げられる。更にタフネス3で罰火にも耐えられるのがいかにも対土地単を意識したスペック。
護衛募集院でサーチができなかったり伝説だったりと一長一短な部分は多いが、メインで入れるとしたらコストやスペック的にセラの報復者と入れ替わりになりそう。
2、覆いを割く者、ナーセット
対戦相手だけに迷宮の霊魂の能力を内蔵したPW。3マナでこちらはアドを取り相手のドローを封じるという動きは、殴れないレオヴォルドのような使い勝手になりそう。主に青系のコントロールミラーでのサイド候補として。
3、リリアナの勝利
ついに悪魔の布告のほぼ上位互換が登場。グリコンではラスアナを使うので布告と完全に入れ替わりで白力線をものともしないのが素晴らしい。
ヴェリアナ・ラスアナを両方取った黒の濃いリリアナコンを組んでみたい。
4、戦慄衆の秘儀術師
トランプルを持っているのに1/3というスペックがミスマッチだが、単純にブレストや稲妻をコストも払わず使い回すだけでも十分強く、生き残ればボブのような使い勝手になりそう。祖先の幻視のような待機呪文を墓地から踏み倒せるのは魅力的なので、その辺りもうまく組み合わせた構築をしたい。
トランプルを活かすには強大化にようなカードでパンプしつつ墓地からもう一度強大化して大ダメージを狙ったり、もしくはウィザードなのでエイデリズでパンプして2〜3マナ域までの呪文を踏み倒す使い方が現実的か。
5、約束の終焉
赤のダブシンという色拘束がキツイので入るデッキは限定されるが、X=1で十分な威力を発揮でき、単純にバーンに入れても3マナで稲妻+チェンライの6点火力として見れば悪くない。戦慄衆の秘儀術師と同様、待機呪文を踏み倒せるのはやはり魅力的なので、できればそれも活かせた構築をしたい。
1枚で合計3つの呪文を唱えられることから、弧光のフェニックスを復活させるためにはおあつらえ向き。URカラーで、ルーティングで祖先の幻視やフェニックスを落とし、これで3ドローしつつフェニックスを復活させるようなデッキを組んでみたい。