エルフの開墾者入りRUGデルバー構築
2019年7月13日 Magic: The Gathering先日の注目カードに挙げていたエルフの開墾者。早速カナスレのマングース枠に入れ替えて回してみましたので今回は使用感と構築、調整について書いていきたいと思います。
まず結論から言えば、想定通りレガシーでも十分に使えるカードパワーを持っていると感じました。クロックを刻めるシステムクリーチャーということで、言い過ぎかもしれませんが構築次第では新世代の死儀礼のシャーマンとなるかもしれません。
実際に回してみて気づいた点についていくつか挙げていきます。
3/4になるためにはこのデッキでは3ターン目以降になるので、基本的にはシステムクリーチャーとしての扱いで出していくことになります。火力があるデッキに関しては最初から3/4になるまでは構えるなどして展開は控えたいところですが、それでも1マナなのでテンポ損にはならないしソープロ耐性は元々ないので、1ターン目に死儀礼を展開していた時と同じように積極的に展開してもそこまで問題ないと感じました。
しかし3ターン目に3/4になるのはややハードルが高く、火力がある相手に対しては自身の能力で積極的に墓地を肥やしていく必要があります。テンポはやや悪くなりますがそこはシステムクリーチャー、構えるメリットも当然あります。不毛をサーチしてきたり、相手の不毛に対しては対象になっている土地をコストに能力を起動できるので耐性ができたり、不毛が効かない相手の場合はフェッチやキャノピーランドに交換しながら墓地を肥やしていくことができます。
そしてひとたび3/4になれば、稲妻圏外になるのはもちろんですがミラーマッチ際のマングースを一方的に討ち取れる他ネメシスにも討ち取られなくなるので、他にタルモのような地上生物を横並びした時でもお構いなしに殴りにいけるようになったのはマングースとの大きな違いと言えます。
メインではこのような使い方でマングースとの差別化を図っていますが、真価を発揮するのはやはりサイド後です。墓地対策にボジューカの沼、コンボ対策にカラカス、コントロール対策に幽霊街等、土地のシルバーバレット戦略を取れる万能さは、冒頭でも述べたようにさながら死儀礼と言っても過言ではないという感覚になります。
開墾者の採用により既存のカナスレで取っているカードで使い辛くなったものもあります。コントロール対策としてカナスレがサイドに採用している冬の宝珠は、マナを食う開墾者とは相性は良くありません。レンと六番との相性を考えるとそのまま採用しても悪くはないですが、開墾者が3/4になる前に出してしまうとなかなか墓地が肥えなくなるのでやや出すタイミングに制限がかかってしまうのがネック。森の知恵や硫黄の渦等の別のカードでの対策を検討する必要があります。
以上を踏まえ、現段階で調整したレシピはこちらです。
4秘密を掘り下げるもの
4エルフの開墾者
2タルモゴイフ
2真の名の宿敵
12
4渦まく知識
4思案
4稲妻
4もみ消し
2呪文貫き
2呪文嵌め
2レンと六番
4目くらまし
4意志の力
30
3Tropical Island
2Volcanic Island
1焦熱島嶼域
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
4不毛の大地
18
SB
1古の遺恨
2燃え殻蔦
1四肢切断
2外科的摘出
1紅蓮破
1水流破
1狼狽の嵐
1夏の帳
1森の知恵
1レンと六番
1ボジューカの沼
1カラカス
1幽霊街
15
サイドボードは、コントロール対策の冬の宝珠は開墾者との相性の関係上不採用とし、代わりに追加のレンと六番・森の知恵と、燃え殻蔦を2枚採用しています。前述の通り、シルバーバレット戦略を取るために1枚挿しの土地を複数採用。レンと六番の枚数も増やすことで使い回しやすくします。
また、M20から注目カードである夏の帳も採用しています。紅蓮破と狼狽の嵐の両方の役割を持たせられてアドまで取れるのが強いので、使い勝手が良ければ増量も考え中。
現在のメタは4Cデルバーやカナスレが台頭してきているので、水没の強さも相対的に戻ってきています。今回は枠の関係上不採用にしていますが、今後は何か削ってでも入れる可能性は十分にあります。
まず結論から言えば、想定通りレガシーでも十分に使えるカードパワーを持っていると感じました。クロックを刻めるシステムクリーチャーということで、言い過ぎかもしれませんが構築次第では新世代の死儀礼のシャーマンとなるかもしれません。
実際に回してみて気づいた点についていくつか挙げていきます。
3/4になるためにはこのデッキでは3ターン目以降になるので、基本的にはシステムクリーチャーとしての扱いで出していくことになります。火力があるデッキに関しては最初から3/4になるまでは構えるなどして展開は控えたいところですが、それでも1マナなのでテンポ損にはならないしソープロ耐性は元々ないので、1ターン目に死儀礼を展開していた時と同じように積極的に展開してもそこまで問題ないと感じました。
しかし3ターン目に3/4になるのはややハードルが高く、火力がある相手に対しては自身の能力で積極的に墓地を肥やしていく必要があります。テンポはやや悪くなりますがそこはシステムクリーチャー、構えるメリットも当然あります。不毛をサーチしてきたり、相手の不毛に対しては対象になっている土地をコストに能力を起動できるので耐性ができたり、不毛が効かない相手の場合はフェッチやキャノピーランドに交換しながら墓地を肥やしていくことができます。
そしてひとたび3/4になれば、稲妻圏外になるのはもちろんですがミラーマッチ際のマングースを一方的に討ち取れる他ネメシスにも討ち取られなくなるので、他にタルモのような地上生物を横並びした時でもお構いなしに殴りにいけるようになったのはマングースとの大きな違いと言えます。
メインではこのような使い方でマングースとの差別化を図っていますが、真価を発揮するのはやはりサイド後です。墓地対策にボジューカの沼、コンボ対策にカラカス、コントロール対策に幽霊街等、土地のシルバーバレット戦略を取れる万能さは、冒頭でも述べたようにさながら死儀礼と言っても過言ではないという感覚になります。
開墾者の採用により既存のカナスレで取っているカードで使い辛くなったものもあります。コントロール対策としてカナスレがサイドに採用している冬の宝珠は、マナを食う開墾者とは相性は良くありません。レンと六番との相性を考えるとそのまま採用しても悪くはないですが、開墾者が3/4になる前に出してしまうとなかなか墓地が肥えなくなるのでやや出すタイミングに制限がかかってしまうのがネック。森の知恵や硫黄の渦等の別のカードでの対策を検討する必要があります。
以上を踏まえ、現段階で調整したレシピはこちらです。
4秘密を掘り下げるもの
4エルフの開墾者
2タルモゴイフ
2真の名の宿敵
12
4渦まく知識
4思案
4稲妻
4もみ消し
2呪文貫き
2呪文嵌め
2レンと六番
4目くらまし
4意志の力
30
3Tropical Island
2Volcanic Island
1焦熱島嶼域
2溢れかえる岸辺
2汚染された三角州
2沸騰する小湖
2樹木茂る山麓
4不毛の大地
18
SB
1古の遺恨
2燃え殻蔦
1四肢切断
2外科的摘出
1紅蓮破
1水流破
1狼狽の嵐
1夏の帳
1森の知恵
1レンと六番
1ボジューカの沼
1カラカス
1幽霊街
15
サイドボードは、コントロール対策の冬の宝珠は開墾者との相性の関係上不採用とし、代わりに追加のレンと六番・森の知恵と、燃え殻蔦を2枚採用しています。前述の通り、シルバーバレット戦略を取るために1枚挿しの土地を複数採用。レンと六番の枚数も増やすことで使い回しやすくします。
また、M20から注目カードである夏の帳も採用しています。紅蓮破と狼狽の嵐の両方の役割を持たせられてアドまで取れるのが強いので、使い勝手が良ければ増量も考え中。
現在のメタは4Cデルバーやカナスレが台頭してきているので、水没の強さも相対的に戻ってきています。今回は枠の関係上不採用にしていますが、今後は何か削ってでも入れる可能性は十分にあります。
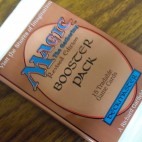
コメント